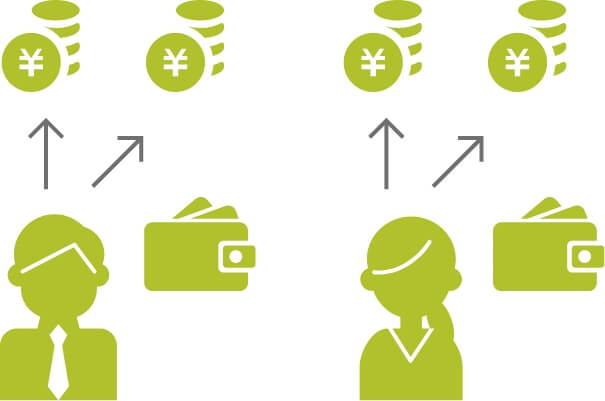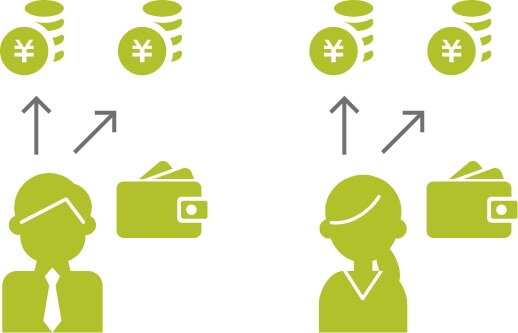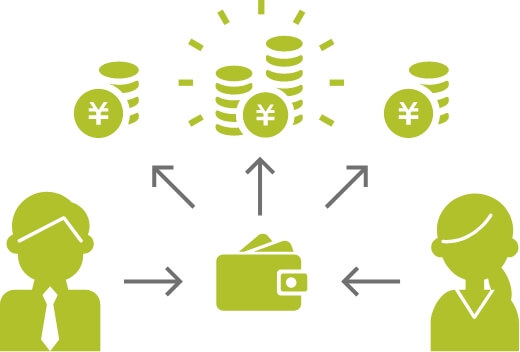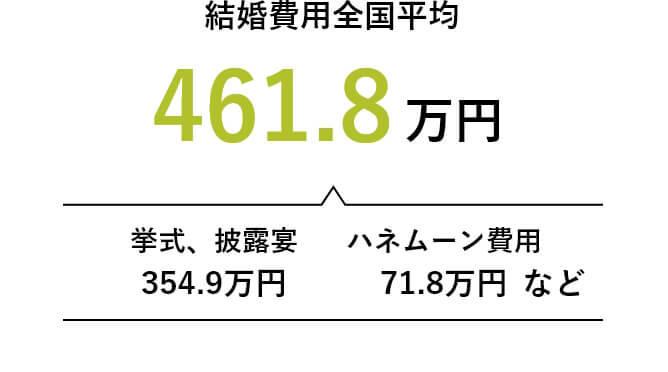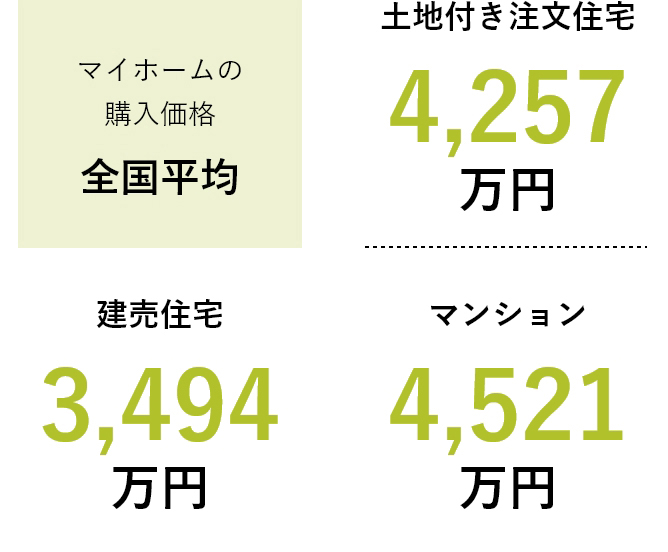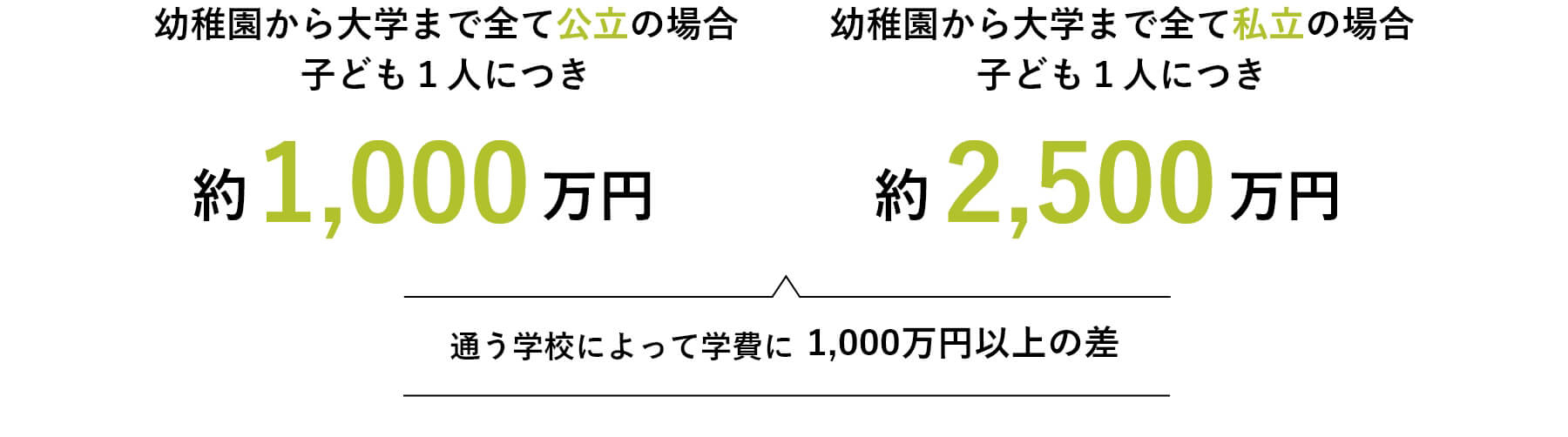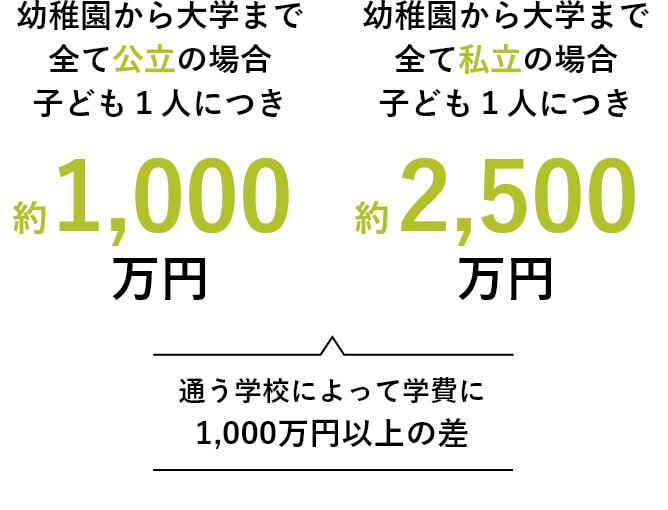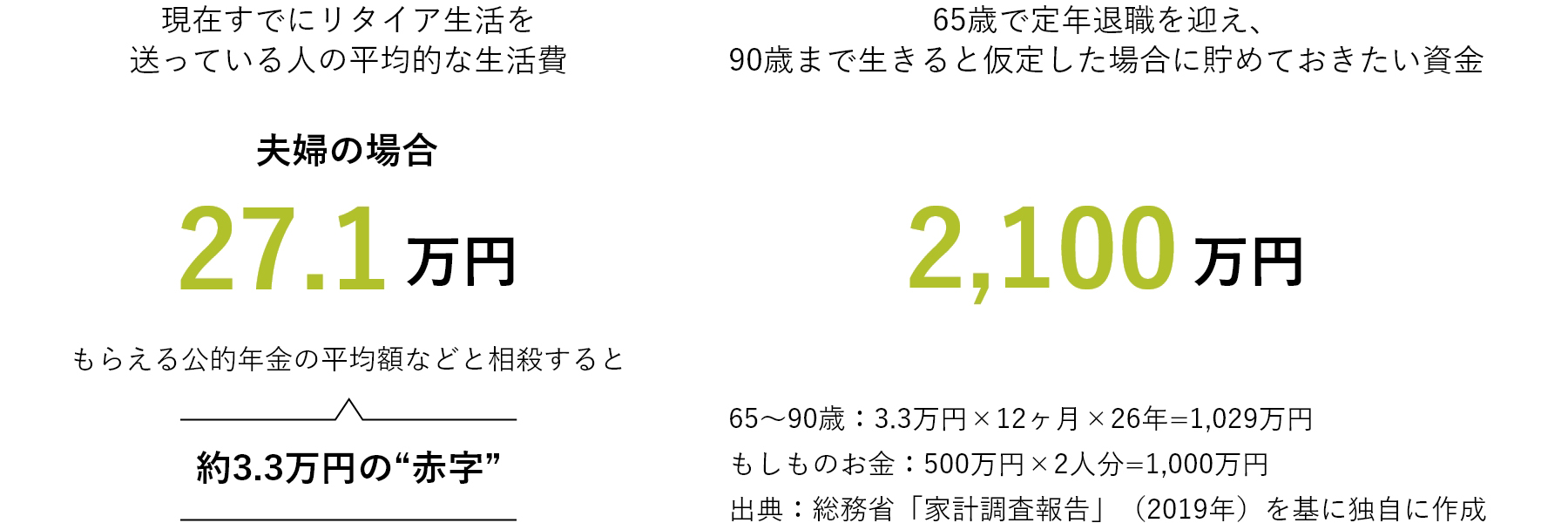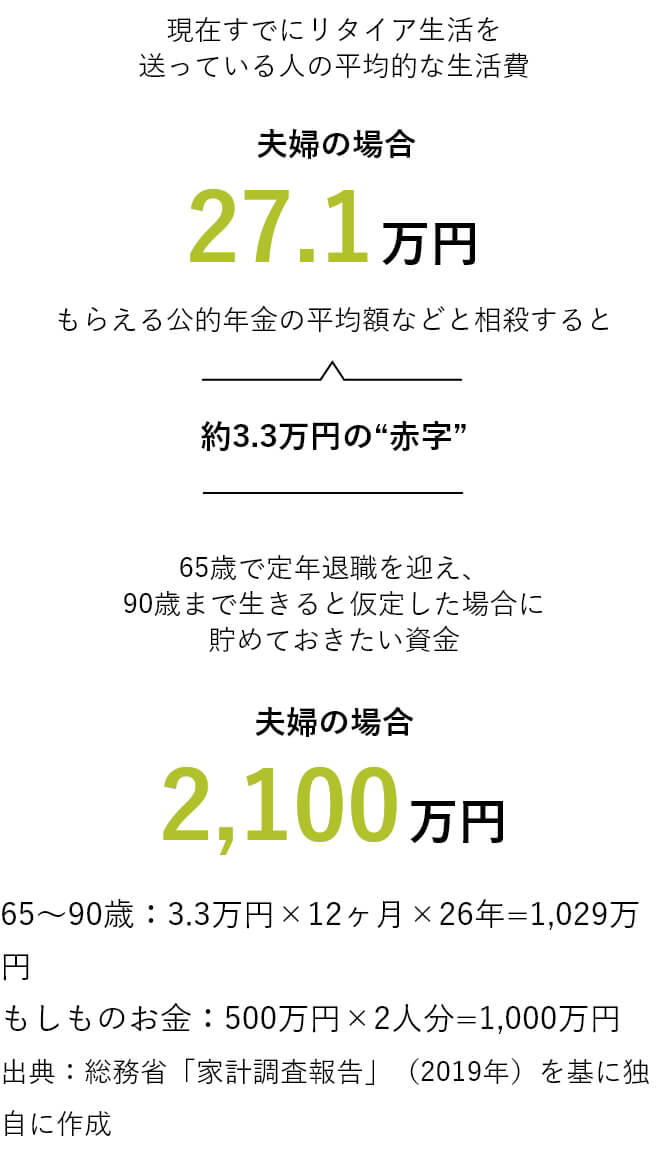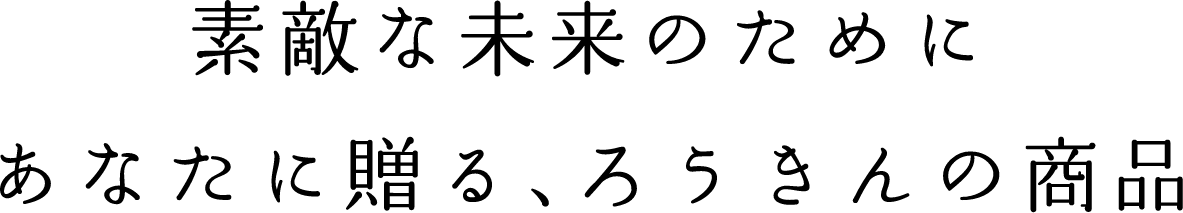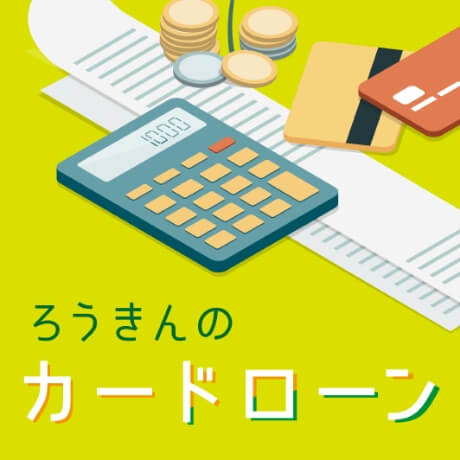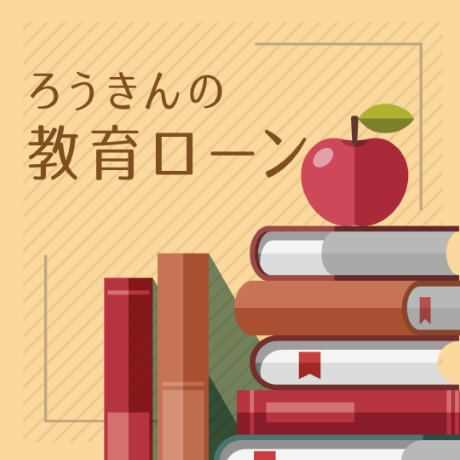(株)Money&You取締役/
ファイナンシャルプランナー
高山 一恵 (たかやま・かずえ)
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー1級
慶應義塾大学文学部卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)
エフピーウーマンを設立し、10年間取締役を務めた後、2015年より現職へ。女性向けサービス、一生涯の「お金の相談パートナー」が見つかる場『FP
Cafe』の事業に注力。全国で講演活動・執筆活動、相談業務を行い、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。