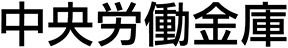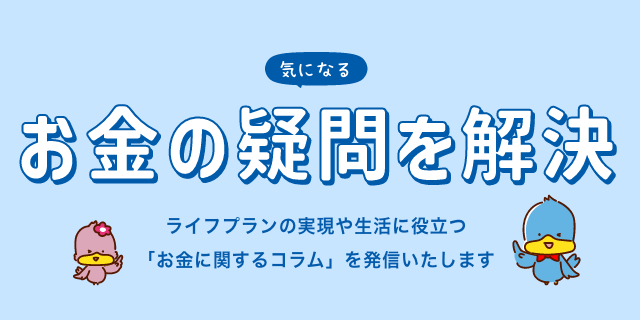投資信託の分配金とは?
種類・選び方・税金などの
基礎知識を解説
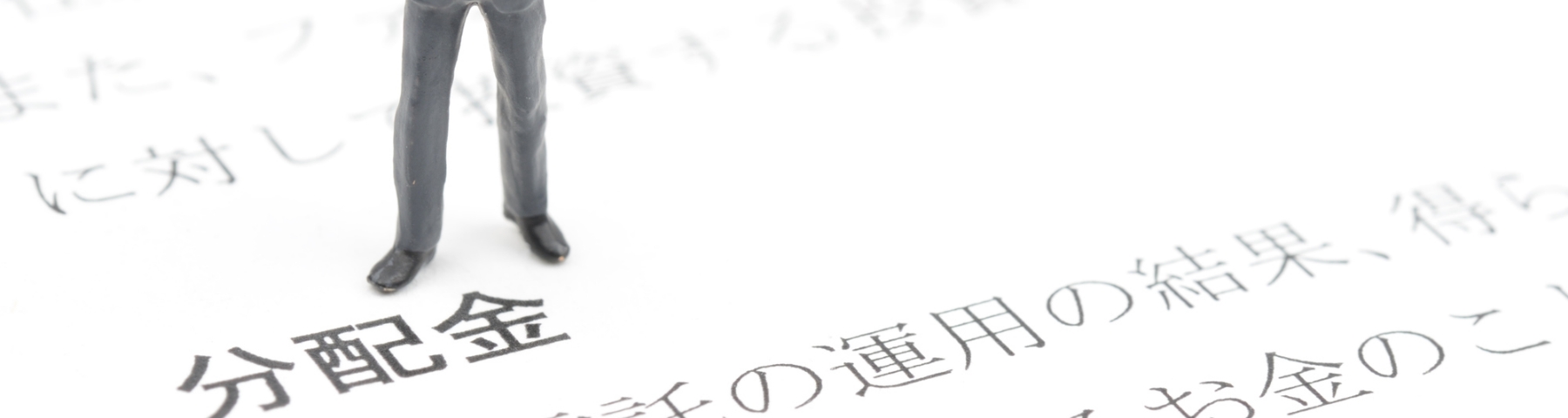
公開日:2025年8月1日
「投資信託の分配金ってなに?」「受け取る時に税金はかかるの?」などの疑問を持つ方に向けて、分配金の基本知識、種類、受け取り方、税金の扱いなどを解説します。
「分配金あり・なし」のどちらを選ぶべきか迷っている方にも役立つ情報を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. 投資信託の分配金とは?
投資信託の分配金とは、投資信託の運用の結果、得られた収益や元本の一部を切り崩し、投資家へ定期的に分配されるお金のことをいいます。
分配の頻度は投資信託によって異なり、毎月、2カ月ごと、年2回、年1回などさまざまです。
1.1. 預貯金の利息・株式の配当金との違い
投資信託の分配金は、銀行などの預貯金から得られる利息や株式の配当金とは、性質・受け取り方などに大きな違いがあります。
投資信託の分配金
投資信託の分配金は、一般的には投資信託の決算時に支払われます。運用状況によって金額が変動し、場合によっては支払われないこともあります。分配を行うかどうか、また、どのくらいの金額を出すかどうかは、各投資信託の約款などに基づき決められているため、あらかじめ決まった金額を定期的に受け取れるわけではなく、必ず受け取れるものでもありません。
預貯金の利息
預貯金の利息は、事前に定められた利率に基づき、定期的に受け取れます。
株式の配当金
株式の配当金は、企業が得た利益の一部を株主に還元するために支払われます。企業の業績等によって金額が決まり、配当がない年もあります。
また、企業によっては、利益が出ていても配当をおこなわず、後日の事業拡大などに備えて、利益を会社内に留保(内部留保)する場合もあります。配当金を求めて投資する場合は、過去の配当実績だけでなく、企業の業績や配当方針も確認しておくことが大切です。
2. 投資信託には「分配金あり」と「分配金なし(再投資型)」がある

投資信託には、定期的に分配金が支払われる「分配金あり」と、分配金を出さずに、得た利益がそのまま再投資される「分配金なし(再投資型)」の2タイプがあります。
「分配金あり」の投資信託では、あらかじめ投資信託ごとに決められた頻度で、分配金が支払われます。ただし、分配金の金額は毎回変動する可能性があり、また、必ず支払われるとは限りません。
一方、「分配金なし(再投資型)」の投資信託は、運用で得た利益を再び運用に回すことで長期的な資産の成長を目指します。
それぞれの分配方針は、投資信託の運用方針を記載した「投資信託説明書(交付目論見書)」に明記されています。投資信託説明書には、分配の頻度や基準価額の推移なども記載されていますので、投資信託の購入前には、それらを必ず確認し、自分の投資方針にあった投資信託かどうか確認しましょう。
3. 分配金の有無の選び方
「分配金あり」と「分配金なし(再投資型)」のどちらを選ぶかは、投資の目的やライフスタイルによって変わります。「今の収入」を重視するか、「将来の資産形成」を重視するかを基準に選びましょう。
3.1. 「分配金あり」が向いている方
「分配金あり」の投資信託は、定期的に収入を得たい方に向いています。
- 定期的なお小遣いがほしい
- 投資の成果をこまめに実感したい
- 長期的な資産形成より今の収入を優先したい
分配金が定期的に支払われることで、投資の成果を実感しやすく、支払われた分配金を日々の生活の中でも役立てることができます。
ただし、分配金がある投資信託は、分配金を出すことで再投資される資金が減り、長期的な資産成長の効果は生まれにくくなる点には注意が必要です。
また、分配金が普通分配金(後述4-1参照)となる場合、税金がかかる点にも注意しましょう。
3.2. 「分配金なし(再投資型)」が向いている方
分配金なし(再投資型)の投資信託は、分配金が支払われず利益が再投資に回るため、資産がより効率よく増えやすくなります。
- 将来に向けて資産をじっくり増やしたい
- すぐに現金収入は必要ない
- 複利効果※を最大限に活かしたい
- 税金の支払いタイミングを先送りしたい
- 長期的な資産形成を重視している
- 複利効果:運用で得た利益(投資信託の分配金など)を引き出さずに、元本に加えて継続して運用(再投資)することによって、資産がより成長していく現象。
分配金を出さない分、途中で受け取れる利益に課税されることもなく、運用資金が最大限活用されるのが「分配金なし(再投資型)」の強みです。特に、老後資金や教育資金への備えなどのため、長期的な資産形成を目的とする方に適しています。
4. 投資信託の分配金の種類

投資信託の分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります。どちらを受け取るかで、課税の有無や実質的な利益に大きな違いがあるため、内容を理解しておくことが大切です。
なお、支払われた分配金が「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」のどちらにあたるのかは、収支報告書(運用状況を知らせる報告書)に記載されている分配金をみれば確認できます。分配金が課税されていたら「普通分配金」、課税されていなければ「元本払戻金(特別分配金)」となります。
4.1. 「普通分配金」
普通分配金は、投資信託の運用で得た利益から支払われる分配金です。基準価額が購入時よりも上回っているときに支払われ、所得税や住民税が課税されます。投資で得た利益とみなされるため、課税対象になります。
- 課税区分:配当所得
- 税率:20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
投資信託取引口座が「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができるため、利用者自身で確定申告の必要はありません。
一方で「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」の場合は、自分自身で確定申告や納税などの手続きをする必要があります。
なお、NISA(少額投資非課税制度)口座で投資信託を購入した場合、普通分配金は非課税(非課税投資枠内での運用に限る)になりますので、分配金を効率的に受け取りたい方にとって、NISAは利用価値のある制度です。
4.2. 「元本払戻金(特別分配金)」
元本払戻金(特別分配金)は、運用益が出ていないときに個別元本の一部を払い戻して支払われます。お金を受け取っていても、実際には元本が減っているだけなので、利益とはみなされず、課税はされません。
5. 「分配金あり」の投資信託を購入する際の注意点
分配金が出ているからといって、必ずしも「得をする商品」とは限りません。購入前に、以下の点に注意しましょう。
5.1. 分配金が多い=得とは限らない
分配金が多いことは投資した方にとってはうれしいことです。ただ、分配金が多くても、投資信託の価格(基準価額)が下がっているときは、元本を取り崩して支払っている「特別分配金」の可能性があるため注意が必要です。
こうしたことから、分配金の多さだけで投資信託の良し悪しを判断するのは危険です。基準価額の動きにもあわせて注意していきましょう。
5.2. 運用資産が増えにくい
分配金は、保有資産の一部から支払われています。そのため、「分配金あり」の投資信託よりも、分配金を出さずに利益が出たら再投資に回す「分配金なし(再投資型)」の投資信託の方が、運用資産の成長するスピードが速くなります。将来の資産形成を重視する方は、「分配金なし(再投資型)」も検討する価値があるでしょう。
6. まとめ
投資信託の分配金には、課税される「普通分配金」と、非課税扱いの「元本払戻金(特別分配金)」があります。普通分配金は運用益に基づく利益の還元ですが、元本払戻金は投資元本を取り崩して支払われるため、「分配金=利益」とは限らない点に注意が必要です。
分配金の有無は、投資目的に応じて選ぶことが大切です。「お小遣いとして使いたい」などという方には、定期的に現金が受け取れる「分配金あり」の投資信託が適しています。一方、「将来に向けて資産を効率よく殖やしたい」という方には、利益を再投資する「分配金なし」がおすすめです。
投資信託選びに迷ったときは、信頼できる金融機関に相談することも有効です。
〈中央ろうきん〉では、目的やライフステージに応じた投資信託を取りそろえています。投資信託について気になることや不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
執筆・監修者

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年8月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ


あなたが最近見たページ
ローンに関するお問い合わせ・
ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでのご相談をご希望の方
ご来店・オンライン相談予約