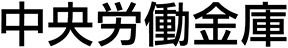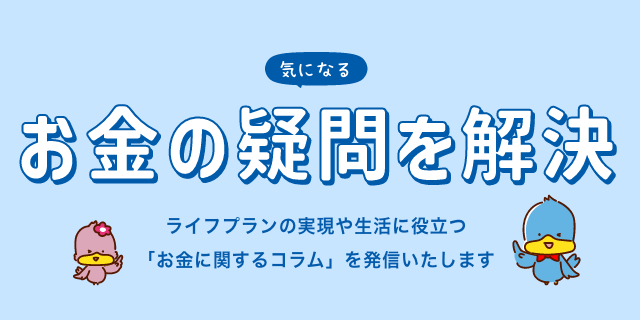遺産相続とは?
法定相続人や相続税、
手続きの流れなど
基礎知識を解説

公開日:2025年7月14日
「遺産相続って、何から手をつければ良いの?」「相続の手続きにミスがあるとトラブルになりそうで不安…」そんな疑問や不安を抱えている方も多いはずです。
遺産相続は、相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から申告・納税までを10カ月以内に行なわなければならず、スムーズに手続きを進めるためには正しい知識が不可欠です。
この記事では、法定相続人の確認方法、遺言書の有無による違い、相続税の計算方法や手続きの流れなど基本的な知識と、トラブルを避けるための対策についてわかりやすく解説します。
1. そもそも遺産相続とは何か
遺産相続とは、亡くなった人の財産や権利・義務を、家族などが引き継ぐ手続きです。亡くなった人のことを「被相続人」、相続財産を引き継ぐ家族を「相続人」と言います。
相続財産には、現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
誰がどの財産を引き継ぐのかは、亡くなる前に被相続人が指示できますし、相続が発生したあとに、相続人の間の話し合いで決めることもできます。なお、民法には、誰が相続人になるのか、どのような割合で相続するのかなどの基本的なルールが定められています。
2. 遺言書がある場合とない場合の違い
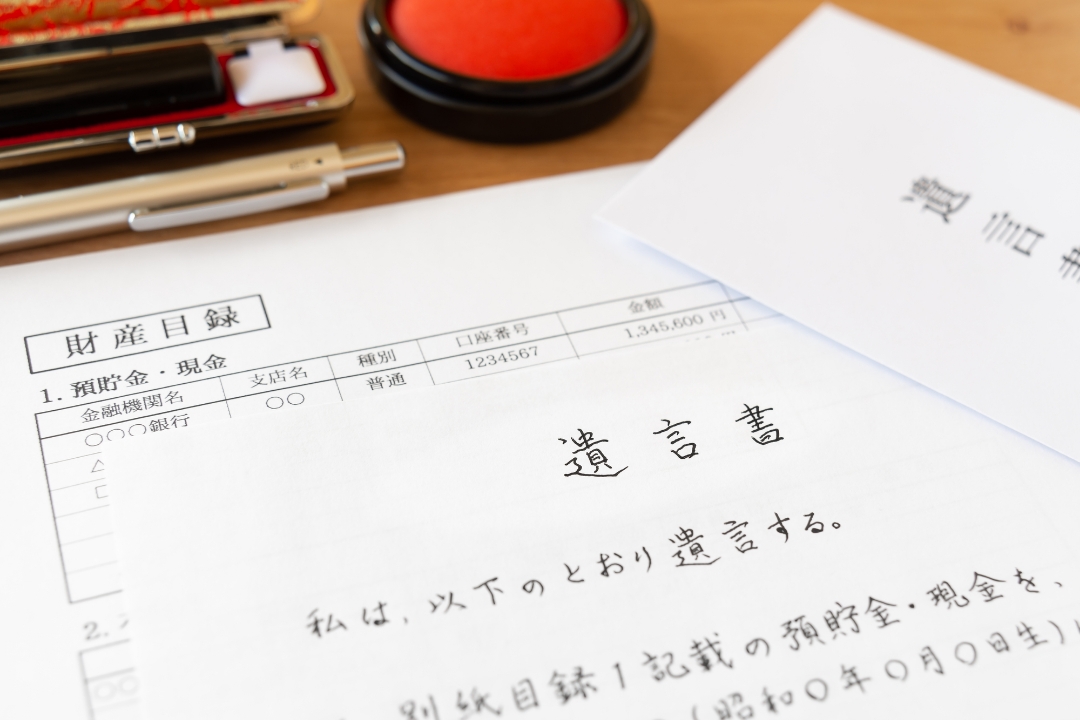
遺言書とは、誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し、その指定に法的効力を持たせるものです。
遺言書がある場合には、法定相続分(民法で定められた相続財産を分配する割合の目安)よりも遺言書の内容が優先されます。財産を残す相手としては法定相続人(民法で定められた相続の権利を持つ人)に限らず、事実婚や内縁のパートナー、血縁関係にないお世話になった方、特定の団体などを指定して財産を遺すこともできます。
遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を実施します。分け方は法定相続分通りでも良いですし、法定相続人全員が合意すればそれ以外の分け方をすることもできます。誰がどの財産を相続するかを決めたら、詳細を遺産分割協議書に記載します。
3. 法定相続人とは?範囲と順位の定め
民法では、「法定相続人」として相続できる人の範囲を定めています。法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と、血縁関係にある「子や孫」「父母や祖父母」「兄弟姉妹」などです。
被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の人は相続上の優先順位が決まっています。被相続人に配偶者と子どもがいれば、子どもは全員相続人になり、遺産は配偶者が「1/2」子どもが「1/2」を相続します。
この時、子どもが複数人いる場合には、子どもの相続分の「1/2」をその人数で均等に分け合います。もし相続人である子どもがすでに亡くなっていて、その人に子ども(被相続人にとって孫)がいれば、その子が相続人となります。
被相続人に子どもがいない場合には、配偶者と両親(もしくは祖父母)が相続人となります。
子どもも、両親もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれの法定相続分については下図をご参照ください。
| 相続順位 | 法定相続人と法定相続分 | |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者が1/2 | 子どもが1/2(人数で分割) |
| 第2順位 | 配偶者が2/3 | 親が1/3(人数で分割) |
| 第3順位 | 配偶者が3/4 | 兄弟姉妹が1/4(人数で分割) |
4. 相続税が発生するか否か
相続が発生しても、遺産額が基礎控除の範囲内であれば相続税を納める必要はありません。ここでは、相続税が発生するか否かの判断基準をお伝えします。
4.1. 基礎控除額と税率の仕組み
財産を相続する場合、相続人の人数に応じた基礎控除があります。相続税の基礎控除額は以下の計算式で計算します。
「相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば、被相続人が配偶者と子ども2人を遺して亡くなった場合、法定相続人は3人となりますので、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
4.2. 相続税計算の基礎となる「課税遺産総額」
相続税は、課税遺産総額(相続税の課税対象となる財産の総額)に対してかかります。
課税遺産総額は、被相続人が所有していた現金や預貯金、不動産などの相続財産に加え、相続人が受け取ることになる保険金や退職金などのみなし相続財産、被相続人が亡くなる以前の7年間に贈与を受けた財産、相続時精算課税制度を適用した財産などの合計から、債務や葬儀費用、非課税財産、基礎控除額などを差し引いて算出します。
課税遺産総額=「相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前7年以内の贈与財産」+「相続時精算課税制度による贈与財産」-「債務」-「葬儀費用」-「非課税財産」-「基礎控除額」
5. 相続全体の手続きの流れ
相続手続きには、さまざまな期限が決まっています。相続を円滑に進めるためにも、どのタイミングで何をやるべきかの全体像を把握しておきましょう。
5.1. 相続開始を知った日から7日以内に必要な手続き
- 死亡診断書(または死体検案書)の受け取り、死亡届の提出
死亡診断書と死体検案書はいずれも効力に違いはありません。
死亡診断書は医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合に発行され、それ以外の場合は死体検案書が発行されます。
死亡届は死亡診断書・死体検案書と一体になっており、遺族が記入して、亡くなった人の死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの役所に提出します。死亡届を提出すると、役所から火葬許可証や埋葬許可証が発行されます。
5.2. 相続開始を知った日から14日以内に必要な手続き
- 年金受給停止の手続き
年金受給者が亡くなった場合には、年金の停止手続きが必要になります。手続きの期限は、厚生年金が相続から10日以内、国民年金が相続から14日以内です。死亡届を提出しないまま遺族が年金を受け取り続けると、不正受給になってしまうため気を付けましょう。 - 世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなった場合には、世帯主変更届を14日以内に住所地の役所に提出します。 - 国民健康保険証の返却
国民健康保険証の返却も14日以内なので、世帯主変更届の提出と併せて役所で手続きしましょう。なお、会社員の人が亡くなった場合、健康保険や厚生年金保険の資格喪失手続きが相続開始後5日以内となっていますが、これらの手続きは基本的に会社がすることになります。
5.3. 相続開始を知ったときから3カ月以内に必要な手続き
- 相続放棄または限定承認の申述書の提出
相続財産には、現金、金融商品や土地・建物のようなプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。これらの相続財産の受け取りをどうするのかという手続きは相続開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所でおこないます。選択肢としては以下の3つがあります。
- ①「単純承認」
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もそのまま相続する方法です。単純承認に手続きは不要ですので、3カ月以内に何の手続きもしなければ単純承認をしたことになります。 - ②「限定承認」
相続によって取得したプラスの財産の限度でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたとき、プラスの財産が残ったら、その分だけ引き継ぐことになります。相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があります。 - ③「相続放棄」
被相続人の財産をすべて相続しない方法です。相続人としての権利を放棄し、マイナスの財産もプラスの財産も受け取らないという選択肢です。放棄する相続人が単独で家庭裁判所へ申述する必要があります。
5.4. 相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に必要な手続き
- 被相続人の所得税に関する準確定申告および納税
被相続人に代わって所得税の申告と納税をする手続きを「準確定申告」と言います。
期限は相続開始を知った日の翌日から4カ月以内で、被相続人の住所地の税務署へ相続人全員でおこないます。なお、準確定申告は、事業所得や不動産所得などがあり、確定申告をする必要があった方が亡くなった場合です。
5.5. 相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に必要な手続き
- 相続税の申告および納税
遺産額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税をおこないます。
遺産分割協議がうまくまとまらない、遺産に土地・建物などの不動産が多く、納税資金がないなどの理由で納付期限を超過してしまうと、延滞税がかかったり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等が利用できなくなるため注意しましょう。申告および納税の手続きは、被相続人の住所地の税務署でおこないます。なお、e-taxや郵送などでも手続き可能です。
5.6. その他の手続き
- 生命保険金の請求
生命保険金の請求は相続開始を知った日の翌日から3年を経過すると時効になります。生命保険金は遺族の生活を守るものであり、相続税のみなし相続財産にもなっているので早めに手続きを済ませましょう。 - 遺族年金の受給手続き
遺族年金の受給にも手続きが必要です。手続きの時効は相続開始から5年となりますので、早めに手続きを済ませましょう。 - 埋葬料・埋葬費の受給手続き
健康保険の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。埋葬料は埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者である必要はありません)に対して、定額5万円が支給されます。埋葬費は死亡した被保険者に家族がいないとき、埋葬を行った人に対して、埋葬料の額(上限5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が支給されます。 - 相続した不動産の名義変更
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。そのため、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請(遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記)をしなければならず、義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。 - 預貯金口座の名義変更および解約
預貯金口座の手続きに期限はありませんが、早めに手続きできれば、被相続人の遺産から相続税を納付することもできます。また、時間の経過で相続関係が複雑になってしまう可能性もありますので、早めに手続きを済ませましょう。 - クレジットカード、電話、公共料金などの解約・名義変更手続き
その他、クレジットカードの解約手続き、固定電話やスマートフォンの解約手続き、公共料金の解約や名義変更手続きなども早めにしておきましょう。放置していると、基本料金や年会費などが引き落とされ続ける可能性もあります。
6. よくある遺産相続トラブルの例

ここから、よくある遺産相続に関するトラブルの例をいくつか紹介します。
6.1. 遺産分割の話し合いがまとまらない
遺産分割協議を実施しても、上手く話し合いがまとまるケースばかりではありません。特に、相続人の間で感情的な対立がある場合には話し合いが難しくなりますし、遺産に土地・建物などの不動産が多い場合には、相続人で等しく分けることが難しく、現金化するために売却が必要になるなど、相続手続きに影響が出ることもあります。
遺産分割の話し合いがまとまらないと財産の処分はできませんが、そのような場合でも、相続税の申告期限は延長できませんので、注意しましょう。
6.2. 遺言書の内容に不満が出る
遺言書がある場合、法定相続分よりも遺言書に書かれた内容が優先されることになります。しかし、その内容が法定相続分から大きく外れる場合などには、相続人の間で不満が出る可能性があります。
相続では一定の相続人について「遺留分」(被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のこと)が認められています。
兄弟姉妹以外の相続人には、「遺留分」が認められているため、遺言書の内容に納得できない相続人がいれば、この遺留分を求めて争いが起きることもあります。
6.3. 生前贈与をめぐる不公平感
生前贈与に関する不公平感もよくあるトラブルの原因です。
例えば、「医学部に進学した兄は塾代や学費として多額の教育費を使ってもらったが、他の兄弟姉妹は最低限のことしかしてもらっていない」「住宅購入時に妹は頭金として多額の援助を受けたが、賃貸を続ける他の兄弟姉妹は何の援助も受けていない」というように、一部の相続人だけが生前にまとまった資金贈与を受けた場合など、話し合いがこじれる可能性があります。
6.4. 相続人の所在が不明・連絡が取れない
遺産分割協議は相続人全員でおこないますが、相続人のなかに長年連絡が取れない人や居場所がわからない人がいると遺産分割協議が難しくなります。
このような場合には、「不在者管財人」の選任を家庭裁判所に申し立て、不在者に代わって遺産分割・不動産売却等を行ってもらいます。なお、不在者管財人は、不在者の財産に関する権利を守る立場ですので、不在者が戻ってきたとき、死亡していることが確認されたとき等に、その役割を終えます。
6.5. 納税資金がない
相続財産の多くを土地・建物などの不動産が占める場合は、手元の現金がなく、相続税が納められないという事態が起きかねません。
相続財産である不動産を売却すれば、相続税は納められます。しかし、不動産が自宅しかない場合では、自宅を売却してしまっては住む場所がなくなってしまいます。相続税がかかることが予想される場合は、あらかじめ納税資金を用意しておくことが理想的です。
7. 遺産相続の準備に役立つ対策と制度
あらかじめ相続対策をしておくことで、相続時の負担を軽減することも可能です。ここでは主な対策について具体的にお伝えします。
7.1. 生前贈与で相続税を軽減する
生前にあらかじめ財産を贈与しておけば、相続発生時の財産を減らせるため、相続税対策になります。
例えば、贈与税には年間110万円の基礎控除があります。そのため、数年かけて生前贈与すれば相続財産を効率よく減らすことも可能です。なお、生前贈与の相手は法定相続人に限らないため、孫たちへの生前贈与や、事実婚パートナー等への生前贈与もできます。
ただし、生前贈与が定期贈与(特定の人に決まった額の贈与を一定期間に渡り繰り返し行うこと)とみなされてしまうと贈与税がかかってしまうこと、生前贈与をしてから7年以内に相続が発生した場合には、その贈与分は相続財産に加算されてしまうことなど、注意点もあるため、事前によく確認しましょう。
7.2. 生命保険を活用する
被相続人名義で生命保険に加入しておくと、相続発生後に死亡保険金という形で現金を用意できます。死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で計算された金額が非課税になるため、節税対策としても有効です。
相続時、手元の現金がないことが想定される場合は、相続人を死亡保険金の受取人にして、生命保険に加入することもいいでしょう。
7.3. 法定相続情報証明制度を活用して手続きを簡素化する
相続手続きでは、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、さまざまな機関に戸除籍謄本等を提出する必要があります。このとき便利なのが「法定相続情報証明制度」です。
この制度は、法務局に戸除籍謄本等の必要書類一式を提出すれば、相続関係を証明する書類(法定相続情報一覧図)を発行してもらえる制度です。以降はこの一覧図を使えば、金融機関や役所で戸除籍謄本等を何度も提出する必要がなくなり、手続きがスムーズになります。
相続が発生してからの手間を減らすために、事前に制度を理解しておくと安心です。ただ、必要書類を用意する手間がかかる、一部金融機関では受付けていないなどのデメリットもありますので、注意も必要です。
7.4. 配偶者居住権で住まいを守る
相続時に配偶者が住むところを失うリスクを減らすために活用できるのが、被相続人の死後も、配偶者が被相続人の自宅に住み続けられる権利を保障する「配偶者居住権」です。
遺産分割で配偶者が自宅を受け継いだとき、自宅の評価が高いと、取り分が圧迫されて他の財産を受け取ることができず、生活費に困るケースがあります。しかし、配偶者居住権を設定すれば、建物の価値を居住権(自宅に住む権利)と所有権に分けて考えることができるため、配偶者が自宅の所有権を持っていなくても、引き続き住み続けることができます。
高齢の配偶者がいる家庭では、安心して住み続けられる環境を整える手段として検討する価値があります。
8. まとめ
遺産相続に関しては、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告から納税までをおこなう必要があります。家族間のトラブルを避けるためにも、法定相続人や財産の種類を明らかにしておき、必要であれば遺言書を残しておきましょう。
また、相続税がかかりそうな場合には、生前贈与や生命保険の活用なども視野に入れて、相続税対策を進めましょう。
〈中央ろうきん〉では、「遺産整理・遺言信託」取次業務をしております。遺言書作成のサポートや専門的なアドバイスを受けることができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
執筆・監修者

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年7月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ


あなたが最近見たページ
ローンに関するお問い合わせ・
ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでのご相談をご希望の方
ご来店・オンライン相談予約