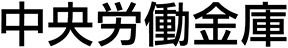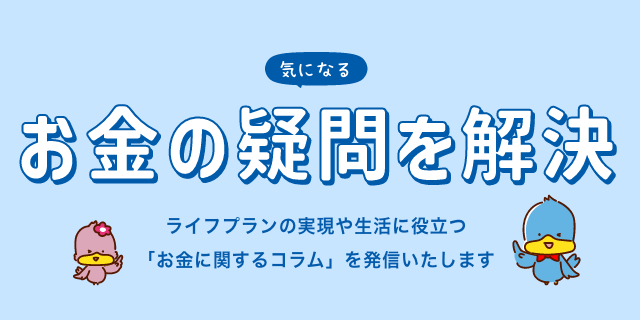投資とは?
投資の主な種類や始める際の
初心者向けのポイントを解説

公開日:2025年3月10日
「投資でお金は増やせるのかな?」「どのような投資が自分に合っているんだろう?」などの疑問があり、投資に興味を持っているけど、実際に始められていない方もいるでしょう。投資には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。この記事では、投資初心者のための、投資の種類ごとの特徴や投資を始める前に知っておくべきポイントを解説します。
1. 投資とは
投資とは、将来的に資産が増えることを期待して、現在ある資金を投じることです。投資は預貯金と異なり元本の保証はなく、利益も確約されていません。
資金を投じる先には、株式や投資信託、証券、不動産、金(きん)などがあります。
2. 投資で得られる収益の種類
投資で得られる収益は、大きく2つに分けられます。「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」と言いますが、その違いを確認しておきましょう。
2.1. インカムゲイン
「インカムゲイン」とは、保有している資産から得られる収益のことです。預金の利息、債券の利子、株式投資の配当金、投資信託の分配金、不動産の家賃収入などがこれにあたります。どれも資産を保有していれば継続的に得られる利益ですが、株式投資の配当金や投資信託の分配金は、企業の業績や資産の値動きなどによって、金額が変動したり、支払われなかったりすることもあります。
2.2. キャピタルゲイン
「キャピタルゲイン」とは、投資対象の資産を購入したときよりも高値で売却して得られる差益のことで、譲渡益や売却益とも言います。株式投資や投資信託、不動産など価格変動があるものを購入したときよりも値上がりしてから売却すると、「キャピタルゲイン」が得られます。ただし、価格に変動がある資産は、値下がりする可能性もあります。このように購入したときよりも、値下がりしてから売却したときに被る損失は「キャピタルロス」と言います。
3. 投資の主な種類一覧

投資には、株式や投資信託、証券、不動産、金など様々な種類があります。ここでは、特に多くの金融機関で取り扱いのあるものと、証券会社以外の金融機関では取り扱いのないものの、それぞれの特徴をお伝えします。
3.1. 多くの金融機関で取り扱っている投資の主な種類
3.1.1. 投資信託
「投資信託」は、投資家が投資したお金をひとつにまとめて資産運用の専門家が運用する金融商品です。運用結果によっては元本割れの可能性がありますが、「インカムゲイン」や「キャピタルゲイン」に期待が持てます。
1,000円~10,000円程度の少額から投資が可能で、1つのファンドには複数の株式や債券が含まれているため、分散投資が実現します。
分散投資とは、複数の投資対象に分けて投資を行うことで、リスク(収益や損失の振れ幅)を抑えられるため、初心者にとってもメリットの多い投資手法です(詳細は後述4.4.参照)。
3.1.2. 個人向け国債
「国債」とは、国がお金を借りるときに発行する債券のことです。「個人向け国債」は個人が1万円から購入できる「国債」で、利子が指定の普通預金口座へ年2回(半年毎)支払われ、固定3年、固定5年、変動10年の3タイプから選ぶことができます。
「株式投資」や「投資信託」などに比べると、国にお金を貸すことになる「個人向け国債」は、それほど大きなリターンは期待できませんが、元本と最低金利が保証されている安心感があるでしょう。
国が破綻しない限り満期時に元本が戻ってくるメリットがあり、安全に資産運用したい方におすすめです。
3.1.3. 外貨預金
「外貨預金」では、外貨(外国の通貨)で預金をします。出し入れ自由な外貨普通預金と、あらかじめ期間を定める外貨定期預金があります。「外貨預金」は比較的高い金利が設定されていますが、預け入れ時は円から外貨に、引き出し時は外貨から円に戻す必要があるため、為替相場の影響を受けます。
例えば、「外貨預金」に預けたときよりも、引き出し時が円安だと為替差益が得られます。一方、預けたときよりも、引き出したときが円高だと為替差損が生じます。この他、円から外貨へ預けたときや、外貨から円に戻すときに為替手数料がかかります。このように「外貨預金」では、金利や為替の動向に気をつけるとともに、手数料についても考慮する必要があります。
3.2. 証券会社以外の金融機関で取り扱っていない投資の主な種類
ここからは、証券会社以外の金融機関では取り扱っていない投資の主な種類について解説します。
3.2.1. 株式投資
「株式投資」では、株式会社が発行した株式を購入し、株主になります。企業は株主からの出資で得た資金で事業拡大を目指し、収益が出ると、株主には配当金として利益の一部が還元されます。
また、株価が上がったタイミングで株式を売却すると、株主は売却益(キャピタルゲイン)を得られます。
「株式投資」では、投資先の企業が収益をあげれば、持ち分に応じた利益の分配を受けられます。一方、業績が悪化すると、配当金はなくなる可能性があります。また、株価も値下がりする可能性があり、株価が下がったタイミングで株式を売却すると、損失を負うことになります。
3.2.2. ETF(上場投資信託)
「ETF」は、Exchange Traded Fundの略称で、「イーティーエフ」と読みます。日本語では「上場投資信託」と訳されます。「投資信託」は通常、注文した翌営業日の売買金額(基準価額)で売買しますが、「ETF」は株式のように相場の値動きを見ながらリアルタイムで売買ができます。
3.2.3. 社債
「社債」は、企業が資金調達のために発行する債券です。投資家は「社債」を購入して企業に資金を提供することで、利子を得ることができ、満期時には元本が返還されます。ただし、「社債」を発行した企業の倒産などにより、投資家への利子や元本の返済が困難になる可能性もあります。購入する際には発行元企業の信用度を確認して投資先を選ぶ必要があります。
3.2.4. FX(外国為替証拠金取引)
「FX(外国為替証拠金取引)」では、2つの国の通貨の為替相場を予測して売買をおこないます。売値と買値の差額による為替差益と、2国間の金利差から生じる差益(スワップポイント)が「FX」の主な収益です。取引をおこなうFX会社に証拠金を預け入れ、その証拠金を担保に、さらに大きな額の為替取引ができます。少額から始められて投資した金額以上の取引ができますが、元本も利益も保証されないだけでなく、証拠金以上の大きな損失が生じる可能性もあるため、注意する必要があります。
4. 投資を始める際のポイント
投資は一か八かのギャンブルではありません。不要なリスクを負わずに長期的に資産を築いていくために、投資を始める前に心得ておくべきことを確認しておきましょう。
4.1. 余剰資金で始める
投資には価格の変動がともないます。投資は、生活費や緊急時に備える予備資金、近い将来に使うことが決まっているお金ではなく、当面使う予定がなく、万が一なくなっても生活に影響しない余裕資金でおこないましょう。まずは少額からはじめて、少しずつ投資に慣れていくことをおすすめします。
4.2. 長期的な資産形成を目指す
金融市場の動向を予測することは難しく、資産価値が上がる局面もあれば、下がる局面もあります。目先の価格変動に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で投資を続けることが重要です。
一般的に、長期運用をすることで、短期運用に比べて投資におけるリターンが平準化され、安定した運用成果が期待できます。
4.3. 少額ずつ積立投資をする
投資信託の積立投資には、まとまった資金がなくても始めやすいという利点があります。さらに、値動きのある投資商品は値段が上がったり、下がったりすることもありますが、積立投資なら投資信託を購入する時期を分散させ、時間をずらして投資を続けるという「時間分散投資」で購入単価の平準化が期待できます。
4.4. 分散投資をする
投資のリスク(収益や損失の振れ幅)を抑えるためには、異なる国や地域、異なる業種、異なる資産など、値動きが異なる投資先に分散投資することが重要です。
投資には「卵を一つのかごに盛るな」という格言があります。もしすべての卵を入れたかごを落としてしまったら、卵は全部割れてしまいますが、複数のかごに分けておけば、割れる卵は少なくなります。一つの投資対象に集中的に投資するのではなく、複数の異なる投資対象に分散して投資することによって、リスクを小さく抑えることができます。
5. 初心者におすすめの投資の種類

初心者がこれから投資を始めるなら、税制優遇のメリットを享受しながら長期・積立・分散投資ができるNISAやiDeCoがおすすめです。両者の違いを理解して、目的に応じて使い分けましょう。
5.1. NISA(少額投資非課税制度)
「NISA(ニーサ)」は、少額から投資を行う方のために2014年1月から始まった少額投資非課税制度です。通常、金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますが、NISA口座で投資した場合には、非課税となります。
NISA口座の非課税保有限度額は生涯を通じて元本1,800万円となり、そこから得られる利益は非課税になります。また、非課税保有期間については無期限となります。
「NISA」には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、投資方法や非課税投資枠、投資対象商品が異なり、それぞれ目的に合わせて利用ができます。まとまった資金で投資を行いたい方は「成長投資枠」、コツコツと積立投資を行いたい方は「つみたて投資枠」の利用がおススメです。また、両方の投資枠を併用することもできます。
5.2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、任意で加入を申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の一つで、拠出した掛金を定期預金や保険、投資信託といった商品で運用します。
拠出した掛金は全額が所得控除の対象になる、運用期間中の利益は非課税、受取時にも控除が適用されるといったさまざまな税制メリットがあります。また、最短でも60歳になるまで引き出せないため、若いうちから老後資金を貯めたい方におすすめです。
6. まとめ
投資は、資産が増えることに期待して資金を投じるため、預貯金のように元本保証ではありませんが、インカムゲインやキャピタルゲインが期待できます。多くの金融機関で取り扱いがある投資信託、個人向け国債、外貨預金は、株式やFXなどに比べると仕組みがわかりやすく、初心者でも始めやすい投資の種類です。余裕資金を使って、まずは少額から資産形成を始めてみましょう。
〈中央ろうきん〉では、NISA・iDeCoなどの投資に関する相談に丁寧に対応しています。ぜひお気軽に相談ください。
監修者情報

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年3月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ