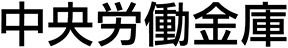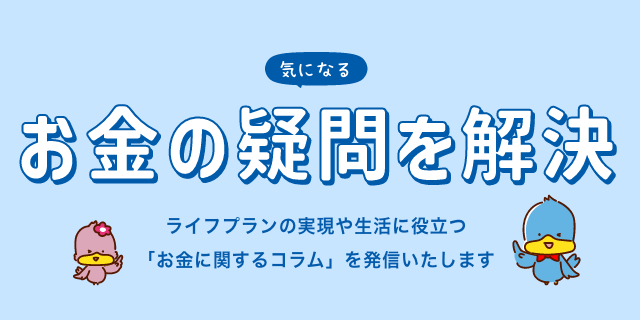金利とは?
主な種類や決まり方から
変動による影響まで解説

公開日:2025年2月19日
普段、何気なく耳にしている「金利」ですが、「金利と利息の違いは?」「具体的に金利ってどう決まるの?」「金利の上げ下げによって暮らしにどう影響が出るの?」などの疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、金利と利子・利息、利率、利回りとの違いや、金利の種類、金利の変動が暮らしに与える影響などについてお伝えします。
1. 金利とは?
銀行にお金を預けたり、銀行からお金を借りたりすると利息(利子)が発生します。この元本に対する利息の割合を金利といいます。金利はお金の預け入れ・借入期間、利息の算出方法、固定金利・変動金利の違い等で異なります。金利の違いによって、受け取る利息や月々の返済額、総返済額は変わってくるため、金利による違いをよく見極めて金融商品を選ぶ必要があります。
2. 金利と似た言葉との違い
金利と似た言葉に、利率・利息(利子)・元金(元本)・利回りがあります。ここではそれぞれの言葉について説明します。
2.1. 利率
利率とは、元金に対する利息の割合です。金利と同様の意味でつかわれることが多く、割合を表すことから、単位は%で表します。1年あたりの利率を年利、1ヵ月あたりの利率を月利といいます。
2.2. 利息・利子
利息や利子は、ほぼ同じ意味で用いられ、お金の貸し借りの際に対価として発生する金額です。利息(利子)は金額を意味するため、単位は日本円の場合「円」で表します。例えば、100万円を1年間、金利1%で借りた場合には、利息(利子)として1万円を支払うことになります。
2.3. 元金(元本)
元金は「がんきん」、元本は「がんぽん」と読みます。いずれも利息を含まない元の金額を意味します。預貯金では、利息が付く前の預け入れた金額、ローンなどの借り入れでは、利息を含まない借り入れ額となります。
2.4. 利回り
利回りは、投資した金額に対する収益割合です。債券や株式、投資信託など投資性のある金融商品で用いられることが多く、投資によって得られる運用利益が投資金額に対してどの程度の割合なのかを表します。
3. 単利と複利の違い
ここでは単利と複利の違いについて説明します。
3.1. 単利
単利は、当初預けた元本に対してのみ利息が付きます。
例えば、単利の運用で金利が年1%の場合、1年後には100万円×1%=1万円の利息がつきます(税金は考慮していません)。2年目以降も金利が変わらない限り毎年、100万円に対して1万円の利息を受け取ることになります。毎年同じ利息がつくため、このケースで10年間に受け取る利息は合計で10万円になります。
3.2. 複利
複利は、元本に発生した利息を組み入れて、次の利息を計算します。そのため、運用期間が長くなるほど、利息は増えていきます。
例えば、複利の運用で金利が年1%の場合、1年後には単利と同様に100万円×1%=1万円の利息がつきます(税金は考慮していません)。翌年は「元金100万円+利息1万円」が元金となるため、金利が変わらない場合、2年目の利息は101万円×1%=1万100円となります。運用期間が長くなるほど1年あたりにつく利息が増えていき、このケースの場合、10年間の利息合計額は10万4,622円になります。
金利が高く、運用期間が長いほど、複利効果が高いと言えます。
4. 固定金利と変動金利の違い

金利には、固定金利と変動金利があります。
4.1. 固定金利
固定金利は、契約時の金利が一定期間または全期間を通じて固定され、変わりません。固定金利のローンでは、固定期間(特約期間)中は市場金利などに左右されることなく同じ金利が適用され、返済額が変わらないため、返済計画が立てやすいメリットがあります。ただし、変動金利よりも通常、金利が高く設定されています。
4.2. 変動金利
変動金利は、市場金利によって適用金利が変動するのが特徴です。一般的に、基準金利(各金融機関が設定するローンの店頭金利)に連動する形で半年に一度、適用金利の見直しがおこなわれます。変動金利は固定金利と比較して通常、金利が低く設定されています。
5. 金利の決まり方
金利は、各金融機関が日本銀行の金融政策や金融市場の動向などに基づき決めています。
5.1. 金融市場の動向と政策金利
金利は経済情勢の影響を大きく受けます。政策金利とは、中央銀行が景気や物価の安定などの金融政策の実現のために設定する短期金利のことをいいます。日本銀行は、この政策金利に基づいて金融機関にお金を貸し出し、金融機関は政策金利や金融市場の動向などに基づき預金や融資の金利を決定します。
一般的に、景気が過熱してインフレ(物価上昇)になると、対策として政策金利を引き上げます。金利が引き上がると金融機関は以前より高い金利で資金調達しなければならないため、企業などへの貸し出しにおいても金利を引き上げるようになります。その結果、企業などは新たな借り入れがしにくくなるため、経済活動が抑制され、景気の過熱を鎮める効果が期待できます。
一方、景気が低迷してデフレ(物価下落)になると、対策として政策金利を引き下げます。金利を下げると金融機関は以前よりも低い金利で資金調達ができるため、企業などへの貸し出しにおいて、金利を引き下げることができます。その結果、企業などは新たな借り入れをしやすくなるため、経済活動が活発になり、景気を刺激する効果が期待できます。
5.2. 個人の信用力と担保の有無
同じ金融機関から同じ金額を借りても、借りる人によって金利が違うことがあります。その理由には、お金を借りる人や企業の信用力、借りる目的、担保の有無などがあります。
お金を貸す側の視点に立ってみると、貸したお金は確実に返済してほしいと考えます。そのため、借入目的や過去の返済実績や資産状況などから相手の信用力を確認し、融資の可否を決定します。信用力が高く積極的に貸したい相手には、金利を引き下げ(優遇)する場合もあります。
また、商品の種類によっても金利が異なります。無担保型のローンの場合には、その使い道によって商品の種類が決まります。車のローンや教育ローンのように使い道の決まっている商品は、カードローンのように使い道の決まっていないローンと比べると金利が低く設定されています。
一方、有担保型のローンである住宅ローンの場合には、住宅に抵当権が設定されており、万が一返済できなくなったとしても、金融機関としては無担保型のローンよりも資金を回収できる可能性が高くなるため、金利は他のローンよりも低めに設定されています。
6. 金利の変動による個人への影響

金利の上げ下げは、私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか。ローンの返済額や貯蓄への影響など複数の視点から考えてみましょう。
6.1. 住宅ローンや自動車ローンなどへの影響
金利が上がると、変動金利で住宅ローンや自動車ローンなどを借りている場合、借入金利が上がって返済額が増える可能性があります。一方、金利が下がると、返済途中で借入金利が下がって返済額が減る可能性があります。
なお、固定金利で借りている場合には、固定期間(特約期間)は借入金利が変わらず、金利変動の影響を受けません。
6.2. 貯蓄への影響
金利が上がると、預金金利も上がる傾向にあります。預金金利が上がれば利息が多くもらえるようになります。例えば100万円を年0.1%で預けた場合、1年間で利息は1,000円となりますが、仮に年利1.0%で預けたら、利息は1万円となります(税金は考慮していません)。
一方、金利が下がると、預金金利も下がる傾向があるため、受け取る利息も少なくなります。
6.3. 消費活動への影響
金利が上がると、借入金利も上がり、支払う利息が増えるため、住宅や自動車などの高額商品を買いにくくなります。
一方、金利が下がると、借入金利も下がり、支払う利息が減るため、ローンを利用して住宅や自動車などの高額商品を買いやすくなります。
6.4. 投資への影響
金利が上がると、金利負担が企業の資金繰りの悪化や企業収益の低下につながりやすく、株価を下落させる可能性があります。また、価格変動のある株式投資などに比べて、預金や債券の魅力が高まり、預金や債券に資金が移ることも多くなります。
一方、金利が下がると、企業にとっては借入コストが下がることを意味します。その結果、収益を出しやすく、設備投資のための新たな借り入れなどもしやすくなり、株価も上がりやすくなる傾向があります。
7. ローンや預金を賢く利用するための金利の注意点
ローンや預金を賢く利用するための金利の注意点について解説します。
7.1. 金利や借入条件等をよく比較して金融機関や商品を選ぶ
新たに借入を検討するときには、複数の金融機関の商品を比較して選びましょう。同じ種類のローンでも、金融機関によって金利や借入条件等に違いがあります。
また、お金を借りる場合だけでなく、お金を預ける場合にも金利や条件等が違うことがあるため、同様によく比較して選びましょう。
7.2. ローンを組む際は金利だけでなく手数料・総支払額にも注目する
住宅ローンの場合、金利以外にも、保証料、事務手数料、団体信用生命保険などの費用がかかる場合があります。
また、返済期間が長期にわたるため、わずかな金利差に見えても総返済額は大きく違うこともあります。借入を検討する際は、金利だけでなく、手数料などの費用や総返済額にも注目しましょう。
8. まとめ
金利の上げ下げはローンの支払利息や預貯金の受取利息に影響し、私たちの暮らしにも密接にかかわっています。日頃から金利動向に関心を持つよう心がけましょう。
執筆・監修者

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年2月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ


あなたが最近見たページ
ローンに関するお問い合わせ・
ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでのご相談をご希望の方
ご来店・オンライン相談予約