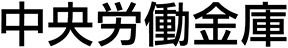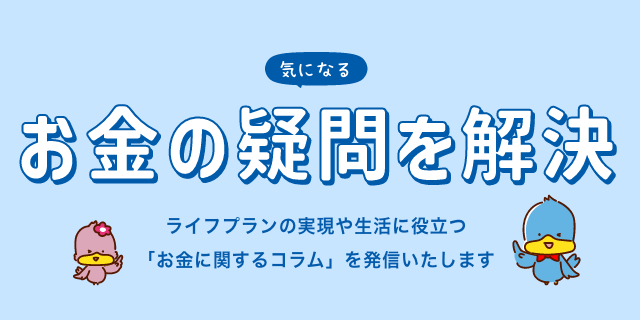【状況別】
退職金の相場|老後の生活が
不安な方に向けて

公開日:2025年3月10日
退職金は、企業が独自に定める制度です。「このまま働き続けてどれくらいの退職金がもらえるのだろう?」「今の会社に退職金制度はあるのか?」など、自分の将来の退職金について疑問がある場合は、勤務先の退職金制度を確認しておきましょう。この記事では、企業規模・業種・勤続年数ごとの退職金相場をご紹介しながら、退職金制度の種類や退職金にかかる税金をわかりやすく解説します。
1. 退職金とは
「退職金」とは、退職する従業員に対して企業が支給する報酬です。退職手当とも呼ばれます。退職金制度は多くの企業で導入されていますが、各企業が独自に定めた制度であり、法律上導入が義務付けられたものではありません。
また、退職金制度がある会社でも、制度の内容や支給額は企業ごとに異なります。退職金制度を導入している多くの企業では、その詳細を就業規則に定め、将来の支払いに向けて長期的に費用の準備をしています。
2. 【企業規模別】退職金の相場
退職金の支給額は、企業規模や業種、学歴、勤続年数等によって差があります。高校・大学の新卒から定年退職まで勤めた場合の退職金の平均額を、企業規模別に見ていきましょう。
| 大学卒 | 高校卒 | |
|---|---|---|
| 大企業*1 | 2,139.6万円 | 2,019.9万円 |
| 中小企業*2 | 1,149.5万円 | 974.1万円 |
- 資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上(運輸・交通関連業種以外)
- 従業員が10人から299人の都内中小企業
出典:中央労働委員会「令和5年賃金事情等総合調査」「令和5年退職金、年金及び定年制事情調査
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
データで平均額を比較すると、退職金額は、学歴による差よりも企業規模による差が大きくなっています。
3. 【業種別】退職金の相場
中小企業を調査対象にした東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」より、業種別、学歴別に新卒から定年退職まで勤めた方の退職金平均額を見てみましょう。
| 業種 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
|---|---|---|---|
| 建設業 | 929.6万円 | 931.2万円 | 991.4万円 |
| 製造業 | 1,107.6万円 | 1,040.5万円 | 1,027.2万円 |
| 運輸業・郵便業 | 938.3万円 | 953.3万円 | 866.1万円 |
| 卸売業・小売業 | 1,239.0万円 | 826.1万円 | 880.7万円 |
| 金融業・保険業 | 1,940.4万円 | 1,521.1万円 | 1,497.0万円 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 1,054.4万円 | - | - |
| サービス業(他に分類されないもの) | 969.1万円 | 1,157.2万円 | 1,213.2万円 |
| 【調査産業合計】 | 1,149.5万円 | 992.0万円 | 974.1万円 |
- 生活関連サービス業・娯楽業の高専・短大卒、高校卒は退職金平均額のデータなし
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
もっとも退職金が多い業種は金融・保険業で、大学卒が1940.4万円、高専・短大卒が1,521.1万円、高校卒が1,497.0万円でした。調査対象となった産業の合計の退職金額は、大学卒が1,149.5万円、高専・短大卒が992.0万円、高校卒が974.1万円となっています。業種によっても退職金額に違いがあるとわかります。
4. 【勤続年数別】退職金の相場
東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」より、学歴別、退職事由別に勤続年数ごとの退職金の相場を見てみましょう。
| 勤続 年数 |
大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己都合退職 | 会社都合退職 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | 自己都合退職 | 会社都合退職 | |
| 10年 | 112.5万円 | 144.8万円 | 102.1万円 | 152.8万円 | 98.5万円 | 126.4万円 |
| 15年 | 209.3万円 | 255.9万円 | 185.6万円 | 227.0万円 | 190.3万円 | 237.3万円 |
| 20年 | 346.8万円 | 408.1万円 | 303.5万円 | 357.8万円 | 288.1万円 | 342.8万円 |
| 25年 | 507.3万円 | 615.6万円 | 437.3万円 | 509.9万円 | 434.2万円 | 510.0万円 |
| 30年 | 750.7万円 | 776.2万円 | 582.2万円 | 663.5万円 | 575.7万円 | 657.0万円 |
| 33年 | 796.8万円 | 889.7万円 | - | - | - | - |
| 35年 | - | - | 721.7万円 | 815.3万円 | 700.8万円 | 790.5万円 |
| 37年 | - | - | - | - | 739.8万円 | 841.9万円 |
| 定年 | - | 1,149.5万円 | - | 992.0万円 | - | 974.1万円 |
- データなしの勤続年数は「-」
出典:東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
勤続年数が長いほど、退職金の支給額が多くなっています。また、自己都合退職か会社都合退職かによっても、退職金の支給額にかなりの差があることがわかります。
5. 退職金の主な種類と受け取るタイミング

退職金制度は、主に退職金が一度に支払われる退職一時金制度と、年金形式で支払われる退職年金制度に分かれます。また、運用方法によってさらにいくつかの制度に分けられます。なかには複数の退職金制度を組み合わせて導入している企業もあります。
制度によって資金の運用方法が異なる他、受け取りのタイミングの選択肢も異なることを理解しておきましょう。また、退職金の管理を外部の金融機関に委託している場合には、受け取りまでの手続きに時間を要する場合があることにも注意が必要です。
5.1. 退職一時金制度
「退職一時金制度」は、定年・会社都合・自己都合・死亡などの理由で退職した従業員に対して、一括で退職金を支払う制度です。
将来の支払いに向けて退職金原資を自社で積み立てる企業もあれば、外部の機関で積み立てる企業もあります。外部の機関で積み立てる方法には、「中小企業退職金共済制度(中退共)」と「特定退職金共済制度(特退共)」があります。
【中小企業退職金共済・特定退職金共済制度】
「中小企業退職金共済(中退共)」とは、中小企業のための国の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営している制度で、常時雇用する従業員数や資本金・出資金の額が一定の範囲内の中小企業が加入できます。加入した企業は、毎月掛金を外部機関で積み立てていきます。そして従業員が退職すると、従業員自身が請求することで、退職金が中退共から従業員に対して直接支払われます。なお、受け取り方法は、一時金払いの他、一定の要件を満たせば全部または一部を分割払いとすることもできます。
「中小企業退職金共済」と似た制度に、「特定退職金共済制度(特退共)」があります。「特定退職金共済制度」も毎月定額を外部機関で積み立てる制度ですが、実施主体が商工会議所や商工会などであること、従業員数や資本金などの企業規模に関わらず導入できるところが「中小企業退職金共済」と異なります。
5.2. 確定給付企業年金制度
「確定給付企業年金」とは、将来の年金給付額があらかじめ確定している企業年金制度で、DBとも呼ばれます。労使の合意に基づいて将来の年金額を設定し、退職金の原資を外部機関で積み立て、運用します。
従業員にとっては将来の受取額が約束されている安心感がありますが、企業にとっては予定通りに運用できなかった場合、不足額を追加で拠出する必要があります。
5.3. 企業型確定拠出年金制度
「企業型確定拠出年金制度」は、主に企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。DCとも呼ばれます。運用先としては、元本確保型の預貯金や生命保険か、値動きのある投資信託から選べます。
企業側の拠出額は決まっていますが、従業員の運用次第で受け取り額が変わる制度のため、従業員が運用のリスクを負います。
6. 退職金の受け取り方法
退職金の受け取りは、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3パターンがあります。受け取り方によって税金のかかり方が異なるため、退職金にかかる税金の仕組みを理解してから受け取り方を選ぶと良いでしょう。
6.1. 一時金受け取り
退職金を一時金で受け取る場合、退職金は退職所得に分類されます。退職金には、勤続年数に応じた退職所得控除が利用できるため、勤続年数が長い人ほど控除額が大きくなり、所得税・住民税の負担が軽減される仕組みです。退職一時金の金額が退職所得控除の範囲内であれば、退職一時金に対する税金の支払いはありません。
| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A (80万円未満の場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(A - 20年) |
- 退職所得は、勤務先から支給された退職一時金等と合算して計算します。
- 退職所得は「退職所得控除額」を超えた場合も、超えた金額の2分の1のみが課税所得として計算されます。
6.2. 年金受け取り
退職金を分割して受け取る年金受け取りの場合、退職金は雑所得に分類されます。公的年金と同じく公的年金等控除を利用するため、企業年金でどの程度の控除を利用できるかは、公的年金の受け取り方や受給額の影響を受けます。公的年金等控除の金額は、65歳未満で60万円から、65歳以上で年間110万円からとなります。
| 年金受給者の年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
| 130万円以上410万円未満 | (A) × 25% + 27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | (A) × 15% + 68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 5% + 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 | |
| 65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
| 330万円以上410万円未満 | (A) × 25% + 27万5,000円 | |
| 410万円以上770万円未満 | (A) × 15% + 68万5,000円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | (A) × 5% + 145万5,000円 | |
| 1,000万円以上 | 195万5,000円 |
- 公的年金等以外に1,000万円を超える所得がある場合は、計算式が異なります。公的年金等以外の所得が1,000万円を超え2,000万円以下である場合には、上記の表の年金額に対応する公的年金等控除額欄に記載された額から一律10万円を差し引いた額が控除額となります。2,000万円を超える場合には、一律20万円を差し引いた額が控除額になります。
6.3. 一時金受け取りと年金受け取りの併用
退職金は、「一時金受け取り」と「年金受け取り」を組み合わせる方法もあります。この場合、「一時金受け取り」部分には退職所得控除、「年金受け取り」部分には公的年金等控除が適用されます。
7. 退職金にかかる税金

勤務先に退職所得の受給に関する申告書を提出すれば、退職所得控除を利用した所得税と住民税を勤務先が源泉徴収して納税するため、原則として、従業員は退職金に関する確定申告をする必要はありません。
退職所得の受給に関する申告書を勤務先に提出しなければ、退職金の支払い金額の20.42%の所得税等が源泉徴収されます。この場合、後日、自分で確定申告をすれば、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
8. 退職金だけでは老後の生活が不安な人へ
老後の生活に不安を感じたら、勤務先の退職金制度を確認するとともに、ねんきん定期便などで公的年金の受給額を確認しましょう。その時点における受給見込み額を確認すれば、退職金のほかに自分で準備すべき金額を考えやすくなります。
また、老後資金を蓄える方法は退職金以外にもあります。ここでは、老後資金を自分で準備する場合の方法を3つご紹介します。
8.1. NISA(少額投資非課税制度)
「NISA(ニーサ)」は、少額から投資を行う方のために2014年1月から始まった少額投資非課税制度です。通常、金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して20.315%の税金がかかりますがNISA口座で投資した場合には、非課税となります。
NISA口座の非課税保有限度額は生涯を通じて元本1,800万円となり、そこから得られる利益は非課税になります。また、非課税保有期間については無期限となります。
「NISA」には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、投資方法や非課税投資枠、投資対象商品が異なり、それぞれ目的に合わせて利用ができます。まとまった資金で投資を行いたい方は「成長投資枠」、コツコツと積立投資を行いたい方は「つみたて投資枠」の利用がおススメです。また、両方の投資枠を併用することもできます。
8.2. iDeCo(個人型確定拠出年金)
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」とは、任意で加入を申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の一つで、拠出した掛け金を定期預金や保険、投資信託といった商品で運用します。
拠出した掛金は全額が所得控除の対象になる、運用期間中の利益は非課税、受取時にも控除が適用されるといったさまざまな税制メリットがあります。最短でも60歳になるまで引き出せないため、若いうちから老後資金を貯めたい方におすすめです。
8.3. 個人年金保険
「個人年金保険」とは、老後に向けた資産形成をするための保険商品で払い込まれた保険料から資金を積み立て、それを原資に契約時に定めた年齢から年金を受け取れます。保険料の払込期間が10年以上あること、年金受取人は被保険者と同一人等の条件を満たした個人年金保険は個人年金保険料控除が利用できるため、所得税・住民税負担を軽減する効果があります。
9. 受け取った退職金の運用例
受け取った退職金は運用していくこともできます。受け取り後、すぐに使う予定がない人は、次の運用方法を検討してみてください。
9.1. 定期預金
「定期預金」とは、あらかじめ預入期間を決めてお金を預ける預金です。中途解約をしない限り、満期までは原則、お金を引き出すことができません。その代わり普通預金よりも通常、金利が高く設定されています。定年退職者を対象に金利上乗せキャンペーンなどがおこなわれている場合もあります。
9.2. 投資信託
「投資信託」とは、投資家が投資したお金をひとつにまとめて資産運用の専門家が運用する金融商品です。
1,000円~10,000円程度の少額から投資が可能で、1つのファンドには複数の株式や債券が含まれているため、分散投資が実現します。
10. まとめ
老後の生活が不安な方は、勤務先に退職金制度があるかどうかや、制度の仕組みや支給額を確認しましょう。退職金の有無や受取金額の目安がわかれば、自分自身で老後に向けて備えるべき金額を考えやすくなります。
また、老後に向けた資金の準備を自身でする場合、NISA・iDeCo・個人年金保険など様々な方法が考えられます。自分に合う制度を見つけ、早めに準備を始めましょう。
監修者情報

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年3月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ