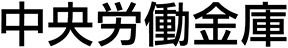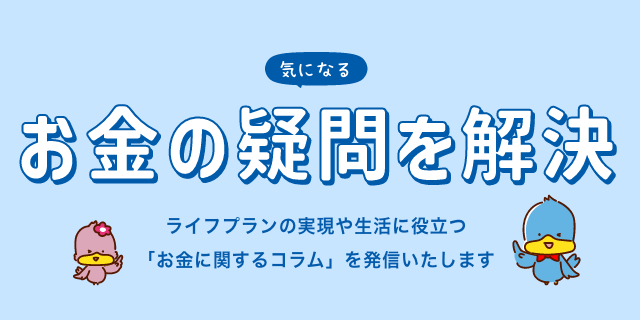貯蓄額の平均はいくら?
年齢や世帯構成別の貯蓄額のデータを紹介

公開日:2025年1月31日
「貯蓄はどのくらいあればいい?」「我が家の貯蓄額は平均以下?平均以上?」など、他の人がどれくらい貯蓄しているか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、年齢別、世帯構成別、地域別など、貯蓄額の平均値や中央値のデータを紹介し、貯蓄額の目安について考えていきます。
- 貯蓄額の平均などのデータは、金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査」(二人以上世帯調査)令和6年版のデータを参照しています。
1. 貯蓄額の平均データを見る前に知っておくべきこと
貯蓄額の平均データを見るときには、年齢や世帯構成など、自分と近い属性のデータを参考にしましょう。ここではデータを見る前に知っておくべきことをお伝えします。
1.1. 平均値と中央値の違い
平均値や中央値は、どちらもデータの中心的傾向を示す数値ですが、その計算方法が異なります。
平均値は、データの値の合計をデータの総数で割った値です。例えば、10人のテストの点数の平均値を求める場合、テストの点数を10人分合計してから10で割って計算します。
ただし、貯蓄額のように個人差が大きくなりやすいデータの場合、対象に著しく貯蓄額が多い人や少ない人が混じっていると平均値に大きな影響を与えます。そのため、最もデータ数の多い数値とズレが生じ、出てきた平均値が誰にとってもしっくりこない数字になりやすい点には注意が必要です。
こうした平均値の欠点を補いたいときには、中央値が利用されます。中央値とは、対象となるデータを小さい順(もしくは大きい順)に並べたときに、ちょうど真ん中に来た数値を指します。
上から数えても下から数えても真ん中のため、中央値は実感に近い数字となりやすい傾向があります。
1.2. 年齢やライフステージによる違い
貯蓄額のデータを見るときには、自分と近い年齢や似たようなライフステージのデータを参照しましょう。
現役で働いている人と、仕事についていない人では家計の状況が異なりますし、若年層と中高年層では収入や貯蓄額なども異なります。
1.3. 世帯構成による違い
世帯主の年齢が同じでも、単身世帯と二人以上の世帯では貯蓄額や支出の内訳には差が生じやすくなります。
また、二人以上の世帯でも、子どもがいる世帯では教育費などがかかる一方、働く大人だけの世帯では収入が多くなりやすく、教育費などは必要ありません。データを見るときには、自分の世帯の構成に近いデータかどうかを確認しましょう。
1.4. 地域による違い
地域によって収入の水準や支出の割合に違いが出ます。例えば、都市部では住居費が高くなりやすく、食費やレジャー費なども高くなりやすい傾向があります。
一方、地方では都市部よりも車の保有率が高まり、自動車関連支出が増えやすい傾向があります。その他、寒い地域は冬場の光熱費が高くなりやすいなどの違いもあります。
地域ごとの家計データには、その地域の暮らしの特性が現れます。お住まいの地域の状況と比較してみると良いでしょう。
2. 【世帯主の年齢別】平均貯蓄額

世帯主の年齢別に貯蓄額を比べると、年齢が上がるにつれて平均値・中央値のいずれも上昇しています。
全体的に平均値の方が中央値よりも高いことから、どの年代でもまとまった貯蓄がある一部の人が、平均値を引き上げていることがわかります。
| 世帯主の年齢 | 金融資産保有額の平均値 | 金融資産保有額の中央値 |
|---|---|---|
| 20歳代 | 508万円 | 185万円 |
| 30歳代 | 909万円 | 360万円 |
| 40歳代 | 1,293万円 | 520万円 |
| 50歳代 | 1,677万円 | 700万円 |
| 60歳代 | 2,581万円 | 1,140万円 |
| 70歳代 | 2,450万円 | 1,205万円 |
3. 【世帯構成別】平均貯蓄額
世帯主の構成別に貯蓄額を比較したところ、平均額・中央値ともにもっとも高いのは就業者がいない世帯です。退職金を手にした定年退職者の世帯などがここに含まれると思われます。
続いて「配偶者のみ就業」の世帯が平均値・中央値ともに2番目に続きます。こちらも、世帯主が定年退職を迎えた後、配偶者だけが勤労収入を得ているケースが一定数含まれていると考えられます。
| 世帯類型別 | 金融資産保有額の平均値 | 金融資産保有額の中央値 |
|---|---|---|
| 世帯主のみ就業 | 1,787万円 | 650万円 |
| 配偶者のみ就業 | 2,108万円 | 850万円 |
| 世帯主と配偶者のみ就業 | 1,488万円 | 628万円 |
| その他就業者あり | 2,003万円 | 800万円 |
| 就業者なし | 2,382万円 | 1,170万円 |
4. 【地域別】平均貯蓄額
地域別の平均貯蓄額を比較すると、関東地方が平均値・中央値ともに最も高くなっています。
| 地域別 | 金融資産保有の平均値 | 金融資産保有の中央値 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,253万円 | 600万円 |
| 東北 | 1,350万円 | 500万円 |
| 関東 | 2,191万円 | 900万円 |
| 北陸 | 1,702万円 | 803万円 |
| 中部 | 1,880万円 | 700万円 |
| 近畿 | 1,830万円 | 860万円 |
| 中国 | 1,397万円 | 600万円 |
| 四国 | 1,722万円 | 575万円 |
| 九州 | 1,344万円 | 710万円 |
5. 理想の預貯金額
金融経済教育推進機構が令和6年におこなった調査によると、手取り年収から預貯金に回す割合は平均で13%です。
これから預貯金を始めようと考えている方はまず、平均値を参考に、手取り年収の10~15%程度の預貯金から始めてはいかがでしょうか。
| 年代 | 手取り年収からの預貯金への振り分け割合 |
|---|---|
| 20歳代 | 14% |
| 30歳代 | 14% |
| 40歳代 | 13% |
| 50歳代 | 12% |
| 60歳代 | 13% |
| 70歳代 | 14% |
| 全年代平均 | 13% |
6. さまざまな状況で貯蓄は必要になる

貯蓄があるかないかで、緊急時や将来のライフイベント時の対応が変わってきます。さまざまな場面を想定し、先を見据えて計画的に貯蓄をしましょう。
6.1. 緊急時のための貯蓄
暮らしのなかでは、思いがけない病気やケガ、失業、盗難などのトラブルに巻き込まれることもあるでしょう。そのようなときには、貯蓄が頼りになるものです。
月の生活費が20万円かかっている方の場合は、生活費の3~6カ月程度、60万円から120万円ほどを金融予備資金として預貯金で確保しておくと安心です。
6.2. ライフイベントに備える貯蓄
貯蓄をする大きな目的の1つに将来のライフイベントへの備えという面があります。ライフイベントには、結婚、車の購入、住宅購入、子どもの進学などがあり、月々の生活費とは別にまとまった費用がかかるので、長い期間をかけて計画的に貯めていく必要があります。
将来、住宅購入を考えるなら、まずは頭金の準備から始めましょう。「2023年度 フラット35利用者調査」によると、住宅購入にかかった資金のうち平均で12.7%を頭金として手持ち資金から支払っています。頭金があることで借入金額を抑えることができ、総返済額を減らすことができます。なお、マンション購入にかかった費用の平均額は5,245万円、土地付き注文住宅の購入にかかった費用は4,903万円となっています。
また、子ども一人あたりの教育費の目安額は、約1,255万円になります。1,255万円の内訳は、幼稚園から高校卒業まですべて公立に進学した場合にかかる費用574万4,201円と、大学入学費用81万1,000円、大学在学費用149万9,000円×4年間の合計額になります。(それぞれの目安額は、文部科学省、日本政策金融公庫の調査結果を参照)
なお、実際にかかる教育費は、公立か私立か、大学の学部が理系か文系か、一人暮らしをするかしないかなどによって大きな差が生じます。教育にはまとまった資金が必要となるので、子どもが産まれたときから計画的に準備を始めましょう。
参照:住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」
参照:日本政策金融公庫 令和3年度「教育費負担の実態調査結果」
6.3. 個人の目標に応じた貯蓄
自分らしい人生を楽しむためには、自分の趣味などにお金を使うことも忘れないようにしたいものです。貯蓄や支出の平均データは参考になりますが、給与の多くを貯蓄に回してしまうと、使えるお金が少なくなって人生を楽しめなくなってしまう可能性があります。何が必要で何が不要か、自分の中で優先順位を決め、不要な部分の支出は減らし、大事にしたい部分に優先的にお金を回すなど、自分らしく家計を調節することで、より充実した日々を過ごしやすくなります。
旅行が好きな人は旅行費を、車が好きな方は車関係費を貯めるなど、目標を明確にして貯蓄をすると楽しみが広がるでしょう。
6.4. 老後のための貯蓄
生命保険文化センターがおこなった意識調査によると、夫婦二人の老後の日常生活費は最低で23万2,000円、ゆとりある生活費は月額37万9,000円となっています。日本年金機構によりますと、老後の主な収入源となる公的年金の平均額は、夫婦二人で月額230,438円となっています。老後ゆとりある生活を送るためには、公的年金以外に月10万円以上が必要となります。
公的年金の不足分を補う資金は、退職金と貯蓄になります。自分の年金額と退職金がいくらになるのかも確認し、計画的に貯蓄をして老後資金を準備しましょう。
参照:公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」
6.5. 毎月の固定費を見直す
毎月決まって出る支出を固定費と言います。固定費には、家賃や住宅ローンの返済、保険料や携帯電話料金、水道光熱費、音楽や動画配信などのサブスクリプション代などがあります。
こうした固定費の見直しは、手間がかかりつい後回しにしがちですが、一度見直せば節約効果がずっと続いて大きな効果が期待できます。固定費を見直して節約できた金額を毎月貯蓄にまわすと、負担なく貯蓄できます。
6.6. 自動的に積み立てる仕組みを作る
貯蓄はいかに意識せず、手間をかけずにおこなうかが継続の鍵です。
給与天引きや銀行の自動積立を利用すれば、毎月の給料日など決まった日に一定金額を預貯金に振り分けることができ、手間をかけずに自然とお金を貯めることができるので、積極的に活用しましょう。
6.7. 目標設定と貯蓄の目的を明確にする
いつ、何のために使うお金かを明確にすると貯蓄のモチベーションにつながります。例えば、旅行のための資金、住宅購入のための頭金、子どもの教育資金、老後資金とでは、お金を使う時期も違えば金額も異なります。
目的を決めて、目的ごとに積立をすると、時間の経過とともに積立額が増えていき、夢の実現が近づいていることを実感できるでしょう。
6.8. 投資を活用してお金を増やす
お金を使う目的や時期によっては、預貯金で貯めるだけでなく、投資でお金を増やすことが向いている場合もあります。特に、余裕資金や老後資金の場合には、長期的な運用が可能となるため、投資で増やすことも考えていきましょう。
また、NISAやiDeCoの制度を使えば、さまざまな税制上のメリットを受けることができるため、少額からつみたて投資も検討しましょう。
7. まとめ
貯蓄を増やしたいと思ったら、まずは固定費を見直したうえで、貯蓄額の平均値・中央値を参考にしながら、自分の目標となる貯蓄額を決めましょう。
将来のライフイベントや老後のためにも自動積立などを活用し、毎月貯蓄していくことを心がけましょう。
〈中央ろうきん〉では、財形貯蓄やエース預金など自動積立の預金を用意しております。これから貯蓄を始めようとお考えの際は、ぜひ〈中央ろうきん〉にご相談ください。
執筆・監修者

氏家祥美
ハートマネー 代表
ファイナンシャルプランナー/キャリアコンサルタント
2005年にFP会社設立に参画しFP相談を開始。2010年に独立してFP事務所ハートマネーを設立。「お金」「キャリア」「聴く力」を強みとして、その人らしい人生地図作りをサポート。子育て世代の貯める仕組み作りから、定年前後の世代まで幅広い相談実績を持ち、人生の転機をサポートしている。
- 本記事は情報提供を目的としており、特定商品の勧誘目的で公開しているものではありません。
- 本記事の内容は、公開日または更新時時点のものであり、その内容を保証するものではありません。
- このコラムは、2025年1月時点の情報を基に作成しています。


よく見られているページ


あなたが最近見たページ
ローンに関するお問い合わせ・
ご相談はこちら
-
店舗・オンラインでのご相談をご希望の方
ご来店・オンライン相談予約