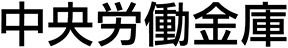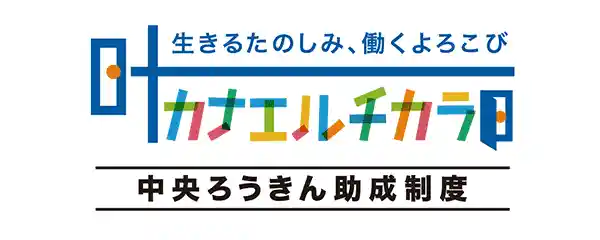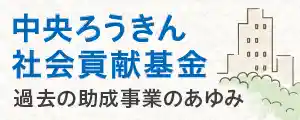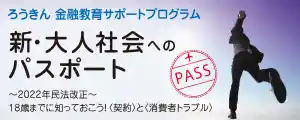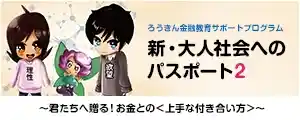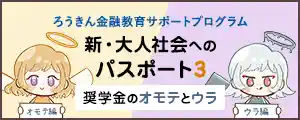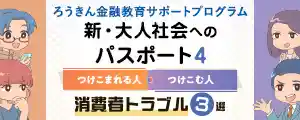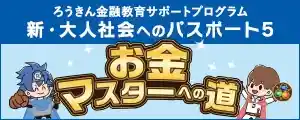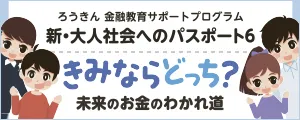2025年 選考結果
選考委員の所感
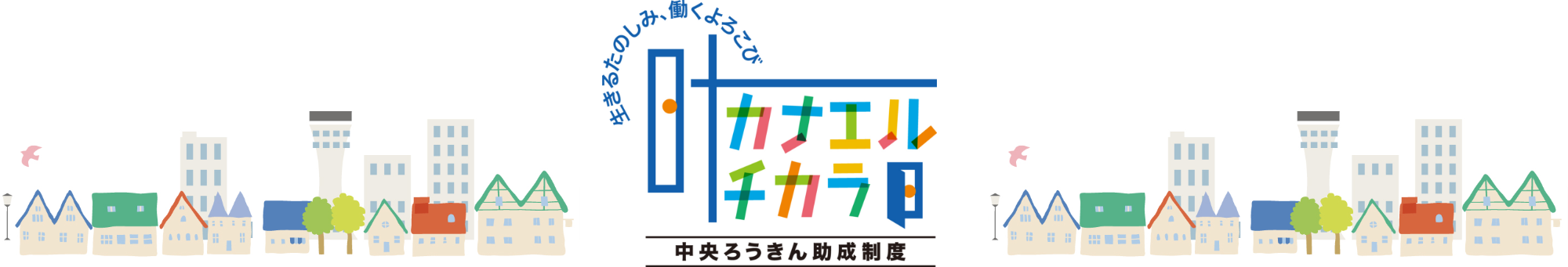
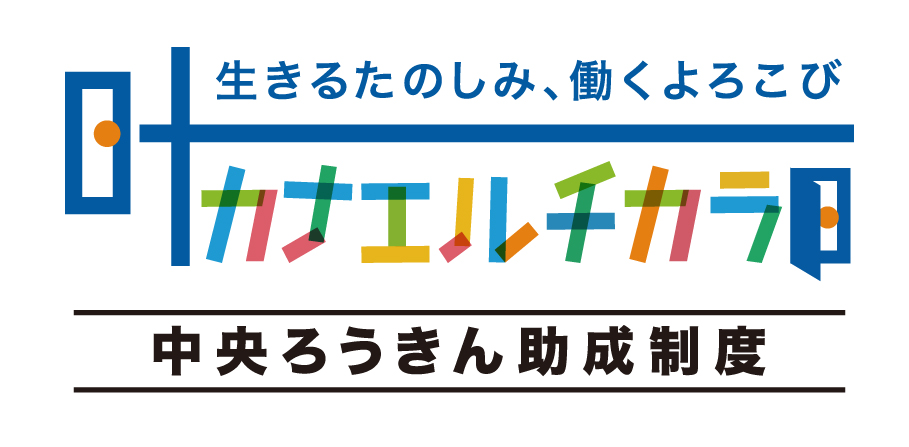
本選考所感
労働者福祉東部ブロック協議会 会長
林 克己

≪プロフィール≫
1981年松下通信工業入社、2000年松下労組通信支部専従
2009年電機連合神奈川地方協議会議長、2013年日本労働組合総連合会
神奈川県連合会事務局長、2023年より会長、神奈川県労働者福祉協議会会長、
2024年より労働者福祉東部ブロック会長。
初めての選考を終えて
中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”に応募頂きありがとうございます。
そして、本年度採択された団体の皆さま、おめでとうございます。
私は、今回初めて本選考に携わることになりました。応募頂いた申請内容を拝見し、それぞれの地域においてさまざまな団体が、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に向けて取り組まれていることと、その事業や活動を〈中央ろうきん〉が支えていることを知りました。選考委員会では、6名の委員にて審議し、それぞれの立場の観点から意見を述べ、1件1件時間をかけ丁寧に議論している姿に感銘を受けました。
私は選考において、最長3年間の継続助成が可能であることを踏まえて、それぞれの団体が本助成制度を活用して、新しい事業を立ち上げながら3年後の姿をどのように描いているかという事業ストーリーを重視させて頂きました。今後の応募にあたり参考にして頂ければ幸いです。
今後も、積極的な応募をお待ちしております。
立教大学 コミュニティ福祉学部
教授 後藤 広史

≪プロフィール≫
博士(社会福祉学)。社会福祉士。認定NPO「山友会」/社会福祉法人特別区社会福祉事業団理事。専門は貧困・ホームレス問題、生活困窮者の「自立」支援。
主な著書に「ホームレス状態からの『脱却』に向けた支援」。
応募団体への敬意と期待を込めて
選考委員として、本年度の中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”にご応募いただいた全ての団体に心から感謝申し上げます。
皆さまが提案してくださった事業は、どれも社会課題に対する深い洞察と創造的な解決策が反映されており、選考を通じてその情熱と取り組みに感動しました。
選考過程では、多くの団体が地域社会との連携を模索し、具体的な活動計画を提示していたことが特に印象的でした。採択された団体の皆さまには、この助成を活用して地域社会の持続可能な発展にご尽力いただくとともに、社会的課題に取り組むためのさらなる財政的な基盤を築いていただきたいと考えています。一方、採択に至らなかった団体に対しても、引き続き支援の可能性を探求し、事業を発展させていくことを願っています。
誰もが生きやすい社会を実現するために、本助成制度を通じて各団体が更なる成果を上げることを心より願っています。
公益社団法人 ユニバーサル志縁センター
専務理事 池本 修悟

≪プロフィール≫
大阪府出身。2000年にNPOを起業。2008年よりNPOを支援する中間支援団体の運営責任者として活動を開始。親に頼れない子ども若者の支援に取り組む。法政大学大学院連帯社会インスティテュート、武蔵野大学EMC等で教員を務め普通の市民が立ち上がり、それぞれが持っている力を結集して、コミュニティの力で社会の仕組みを変えていくコミュニティ・オーガナイジングの普及啓発を行う。
中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”の採択団体はろうきんの社会資源を開くカギとなる!
選考委員会を通じて改めて応募団体、中間支援団体、〈中央ろうきん〉がお互いのことを知り、しっかり連携することで活動の幅が広がることを強く感じました。
本助成制度において助成金は大事なのですが、それだけで応募団体のミッションを達成することは難しいと思います。
〈中央ろうきん〉には労働組合や生活協同組合などとの繋がりはもとより、多くの職員さん、店舗、ATMなど挙げていくときりがない社会資源の宝庫です。この資源を普通は誰も知らないですし気づけないです。しかし選考過程で職員の皆さんや中間支援団体が大切な活動だと感じた採択団体の皆さんは、きっと労働金庫が持つさまざまな社会資源の扉を開くことができると思います。
震災、新型コロナ、戦争、紛争などによって弱い立場の人々に理不尽にさまざまな社会課題が絶え間なく降り注がれますが、これからも本助成制度で繋がった仲間とともに、支え合いながら活動を推進していきましょう。
一般社団法人 SDGs市民社会ネットワーク 理事・事務局長
新田 英理子

≪プロフィール≫
民間企業で3年半働いた後、現在の認定特定非営利活動法人日本NPOセンターでの20年の職員勤務を経て、2017年4月より、SDGs市民社会ネットワークにかかわる。NPO法に関する活動や企業、行政、NPOのパートナーシップにかかわる全国的な活動を経て、現在は、SDGs推進に市民社会組織視点を盛り込む政策提言活動を行っている。法政大学人間環境学部非常勤講師。
当事者視点の活動の重要性
中央ろうきん助成制度“カナエルチカラ”は、他の助成制度とどこが違うのだろう。ということを念頭に置きながら選考基準に従って書類選考を進めました。選考委員会での意見交換は、大変真摯です。
私の立場や役割は、SDGsを推進している市民社会組織の視点から、世界が、日本が、地域が、かつて経験したことのない「変化」の時代を迎えている中で、応募団体が何をやろうとしているのかを、私自身もNPOという立場に身を置きながら、考え、選考する事だと思っています。
本助成制度のサブタイトルは、~生きるたのしみ、働くよろこび~です。
SDGs目標8は、包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセントワーク)の達成です。私たち自身が、ボランティアの現在的価値を踏まえたうえで、「働く」とは何か?に向き合う大切な時間となりました。
応募いただいたすべての団体の皆さんとともに平和で公正で包摂的な社会とはどのような社会なのかを考え続け、行動していきたいと思います。
中央労働金庫 総合企画部(CSR)担当部長
渡邊 泰男
≪プロフィール≫
東京労働金庫に入庫。都内2店舗勤務後、約10年間、本部勤務を行う。その後、神奈川地区2店舗で勤務し、2019年3月から総合企画部でCSRに関する業務(NPO融資相談・金融教育教材の制作・ダイバーシティ推進など)を担当。2022年9月より現職。
より良い社会を目指して、頑張る皆さんを応援したい
各地区で例年を上回る多くの団体の皆さまからご応募いただきましたことを、感謝申し上げます。応募書類を拝見し、団体の熱意や取り組みに対する意欲を感じることができました。選考にあたり、各応募事業を見極めるうえで重要な指標としたのは、選考基準である新規性、必要性、実現性、協力性、発展性の5つの要素です。
新規性においては、従来の枠を超えた新しい試みやチャレンジを評価し、必要性では地域や社会のニーズにどれだけ応えられるかを重視しました。また、実現性については、具体的な計画や組織体制の確保、これまでの事業実績を確認し、協力性は他団体との連携や地域との関係を構築できているかに注目しました。発展性に関しては、応募事業が将来的にどのように成長し、持続可能な形で展開されるかを大きなポイントとしました。
選考を通じて、多くの素晴らしい想いや情熱に触れ、今後の社会に貢献する可能性を強く感じております。応募団体の皆様には、選考結果に関わらず、これからの活動を心から応援いたします。皆さまの取り組みが実を結び、より良い未来を築く一助となることを願っています。
都県選考所感
茨城地区
〈中央ろうきん〉会員団体
各団体とも地域・社会貢献のために目を見張る活動をしており、とても感銘を受けました。
さらには本助成制度を活用し、新たな取り組みや、支援の拡充などを試みる団体もあり、選考では大変悩みました。
子どもの貧困や少子高齢化、さらには人口減少など、地域の抱える課題は山積していますが、今回応募いただいた全ての団体がさらなる発展を遂げ、事業が成功することを切に願っております。
地域NPO支援組織
行政が制度化されておらず、公的財源で予算化されていない地域課題に対し、市民の力を集めて果敢に取り組もうとする、本助成制度ならではの事業が集まりました。
一方、自主財源を拡充するための工夫があまり見えない応募も少なくありませんでした。助成金は一時的な外部応援資金ですから、助成対象期間終了後も活動を継続させるため、受取会費や寄付、事業収益など助成金以外の収益を助成対象期間中にどのように広げるのか、その具体的な方法も申請書類にぜひ記載してほしいと思います。
皆さまの素敵な活動が、持続可能になるよう期待します。
〈中央ろうきん〉茨城県本部
多くの団体よりご応募いただき、少しずつ“カナエルチカラ”の認知度が上がってきていることを、大変嬉しく感じております。申請書類を拝見し、地域が抱えるさまざまな社会的課題に対する支援活動やユニークで新しい試みにチャレンジする姿勢に感銘を受けました。
引き続き、より多くの団体から本助成制度の趣旨でもある「生きるたのしみ・働くよろこび」に共感して、応募いただけることを心より願っております。
今回応募いただきました全ての団体のご発展とご活躍を祈念申し上げます。
栃木地区
〈中央ろうきん〉会員団体
アフターコロナで社会活動が戻るなかで、今年度も多数の応募をいただき安心しました。各団体が悩みや問題を抱えている人に寄り添う活動を選考するにあたり、申請書類から読み解くことが難しい場面もありましたが、各選考委員の意見を参考に本選考委員会へ推薦する団体を決めることができました。
また、今回の選考を通じて、フリースクールの必要性や子育て環境の変化についても再認識し、当事者の方々を支える助成事業の運営のためにも本助成制度の存在意義を痛感しました。
採択された助成団体におかれましては、目標に向かって頑張っていただき、今後の地域社会に与える波及効果に期待します。
地域NPO支援組織
応募いただいた助成事業・活動に取り組むことにより、自団体のみならず、人々の暮らしや地域社会に対してもたらされる好影響について、より具体的に知りたいと思う申請書類が散見されました。限られた紙幅ではあるものの、活動実績を過不足なく記載することで、その説得力は格段に増すと思われます。
「生きるたのしみ、働くよろこび」を感じられる社会の実現に向けて、今後もそれぞれが持てる力を十分に発揮していただけることを願ってやみません。
〈中央ろうきん〉栃木県本部
今回都県選考を実施するにあたり、応募いただきました全ての団体が受益者に寄り添った活動を継続されていることに感銘を受けました。また、地域社会でのNPO支援組織の活動が不可欠であることも、選考を通じて深く感じ取ることができました。
都県選考委員会では、選考委員の皆さまとさまざまな角度から議論を交わし、最後まで悩みながら選考させていただきました。
今回助成の対象とはならなかった団体も含めて、ご応募いただいた全ての団体の更なるご活躍とご発展を祈念申し上げます。
群馬地区
〈中央ろうきん〉会員団体
今回も多くの団体から応募をいただきました。申請書類からは、それぞれの団体の想いがひしひしと伝わってくるものばかりでした。
地域社会が抱える多くの課題として、少子高齢化や地域の過疎化、コミュニケーションの希薄化などに向き合い、乗り越えていこうと活動する各団体の姿に深い感銘を受けました。
「生きるたのしみ、働くよろこび」この活動を体現していただける各団体の今後のご活躍と、その活動に携わる全ての皆さまの「幸せ」を心より祈念申し上げます。
地域NPO支援組織
都県選考を実施するなかで、新たな取り組みを知る度に、市民活動の可能性の広がりを感じます。また、新しい事業や活動を知ることが、市民活動の場における最新の動向を知る上で貴重な情報源となっております。
これまでマッチングすることのなかった分野と人々が、新たな活動を通して出会い、意欲を持って事業に取り組むことは、人々の生きがいや喜びにつながるでしょう。
本助成制度によって、こうした取り組みが一つでも多くなり、地域活性化につながることを祈念いたします。
〈中央ろうきん〉群馬県本部
今回の選考にあたり、応募いただいたすべての団体がさまざまな観点から社会問題を意識し、強い思いと目的を持ち、活動をされていることを改めて実感しました。それぞれの活動をより多くの人々が知り・理解し、活動の輪が拡がっていくことが重要であると考えます。
本助成制度が一人でも多くの方の「生きるたのしみ、働くよろこび」につながれば幸いです。
ご応募いただいた団体の更なるご発展と活動に携わっている皆さま方のご健勝を心より祈念申し上げます。
埼玉地区
〈中央ろうきん〉会員団体
多様な背景を持つ社会的弱者の見守りと居場所づくりに関する多くの意義深い事業と活動を選考する機会を得て、大変感謝しております。
これらの事業は、さまざまな立場の人々に温かい支援と安心を提供し、誰一人取りこぼすことなく地域社会の調和と発展に寄与するためのものと受け止めました。
応募者の情熱と創意工夫に深く感銘を受け、これらの取り組みが地域の生活の質を向上させることを心から期待しています。
今後も、このような意義深い事業と活動が多く生まれることを願っております。
地域NPO支援組織
埼玉地区の応募件数が、昨年に比べて倍以上に増えてほっとひと安心しました。一方で、採択される団体の倍率は高くなりました。
選考において、応募事業・活動の動機や背景は理解できるのですが、これまで実施していた既存事業との違いが分かりにくく、どのように選考したら良いか悩む申請書類もありました。自団体の強みを生かした新たな事業であれば、3年間継続して助成を受けられるチャンスがあるのが、本助成制度の特徴です。団体内で、自分たちが実施したい新たな事業を日頃から話し合い、アイデアを企画メモとして残しておく努力なども大切だと思います。
〈中央ろうきん〉埼玉県本部
ご応募いただきました各団体の内容を一つひとつ拝見させていただき、どの団体からも活動に対する思いや熱量を感じることができました。
また、例年に比べて1年目(新規)のご応募を多数いただき、大変嬉しく感じたのと同時に、どの団体の活動もテーマや内容は異なるものの、どれも社会や地域の課題解決にとっては、必要な活動であることを感じました。
最後に、ご応募いただきましたすべての団体の今後のさらなるご活躍とご発展を祈念申し上げます。
千葉地区
〈中央ろうきん〉会員団体
2025年度助成団体の皆さま、おめでとうございます。また、本助成制度の趣旨に賛同され、熱心に申請書類を作成いただいた全ての団体の皆さま、大変お疲れ様でした。さまざまな支援を必要とする方々が後を絶たない環境下で、多くのチャレンジや新しい試みが寄せられ、社会性や発展性、自主性などの観点から、選考委員会で議論が尽きなかったことがとても印象に残っています。
今回、応募いただいた全ての団体が、事業目標を達成されることを祈念申し上げます。
地域NPO支援組織
応募いただいた申請書類を読み解くなかで、現代社会に不足していることを多く気づかされる場面があります。
今回の選考では、障がいのある子どもたちの暮らしや、障がいのある方々にとって自分らしく働ける環境などについて考えさせられました。彼らが持つ力を十分に発揮できる社会にするためには、どのような環境整備や周囲の理解・支援が必要か、公的な制度や支援ではカバーできない部分をどう補完できるかを、これからも一緒に考えていきたいと思います。
本助成制度を通じて、地域で活動する団体が具体的な取り組みを実現し、地域社会の理解と支援を広げていけることを願っています。
〈中央ろうきん〉千葉県本部
今回ご応募いただきました全ての団体の志に深く感銘を受けました。
NPO団体の皆さまの課題認識とその実行力は、現在の多様な社会のなかで大変役割が大きいと改めて実感いたしました。
選考結果に関わらず、今回ご応募いただきました全ての団体の皆さまのさらなる発展・ご活躍を心より祈念申し上げます。
東京地区
〈中央ろうきん〉会員団体
衣食住やエネルギーなど私たちの生活に大きく係る物の価格が高騰を続け、生活自体が大変厳しい現在、そのなかで生まれた数々の課題に対して、解決に向けた取り組みを日々行っていらっしゃる諸団体の皆さまにあらためて感銘を受けました。
この助成制度もさまざまな形で浸透し、多くの諸団体から多様な事業目的への応募があったなかで、本制度の大きな趣旨である「生きるたのしみ、働くよろこび」を柱に、一つひとつを悩みながら選考させていただきました。
応募いただいたすべての団体の「サポート」によって、一人ひとりの心のなかへ「生きるたのしみ、働くよろこび」という思いあふれる熱意と行動力で目標に向けた活動をさらに期待しています。
地域NPO支援組織
応募いただいた多くの申請書類から、生活者の視点に立ち、地域の課題解決を目指そうとした活動を行っている様子が読み取れました。
子育て支援や若者支援、障がい者の支援など、さまざまなテーマからのアプローチがみられました。それらの活動においては、多様な人たちの参加によって、孤立を防ぐ空間となる「居場所づくり」につながるような工夫を試みている取り組みが多く見受けられました。
新型コロナウイルスの感染拡大で、一度は分断してしまった人と人とのつながりを、改めて構築することで、豊かな地域社会がつくられていく可能性を感じることができました。
〈中央ろうきん〉東京都本部
地域の課題に対する支援に向け、活動している団体の皆さまに敬意を表します。
応募いただいた各団体の活動内容や応募概要を拝見し、さまざまな支援の形があることを改めて学ぶことができました。本助成制度を通じた新しい活動の展開を期待しています。
最後に、今回ご応募いただいた団体の皆さまのご活躍により、生きるたのしみ、働くよろこびにつながる活動の輪がさらに広がることを心より祈念申し上げます。
神奈川地区
〈中央ろうきん〉会員団体
応募された団体の皆さまにおかれましては、現代のさまざまな社会課題に対応した素晴らしい取り組みを展開されていることに敬意を表します。
本選考では、ただの選考作業に終始せず、一つひとつの諸課題の具体的な状況を選考委員のみなさんと共有させていただきました。今後も、個人としてできること、労働組合としてできることを再度見つめ直し、中央ろうきん・応募団体の皆さまとともに、より多くの方の「生きるたのしみ・働くよろこび」の創出に努めていくことをお誓いし、所感と代えさせていただきます。ともに頑張りましょう!
地域NPO支援組織
応募団体にとって助成金は、ありがたい資金源として活動に必要な大きな力となります。また、効果はそれだけに留まらない事はご承知のとおりです。それは助成の目的と自分達の目的は合致しているのか、目的を達成するための事業計画・予算は大丈夫か。これらを見える化し、内部共有を図る。そして第三者の目に触れることを意識して申請書へと落とし込む。この一連の作業は団体の活動のさらなる発展、見直しにとても重要な作業となります。
このことをご理解いただくと、今回採択されなかった応募団体にとっても、決して申請書類を作成することが面倒なものではなくなってきます。ぜひその機会だと思ってください。
〈中央ろうきん〉神奈川県本部
多種多様な団体よりご応募いただき、地域が抱える課題の解決に向け、想いを持って、主体的かつ継続的な視点で事業を運営されている様子を伺うことができました。
また、どの団体も素晴らしい活動を展開しており、申請書類から皆さまの熱い想いを感じることができました。
ご応募いただきました全ての団体の更なるご活躍とご発展、皆さまの素晴らしい活動が地域全体の活性化につながることを祈念申し上げます。
山梨地区
〈中央ろうきん〉会員団体
現代の日本が抱える課題である、子どもの問題や過疎化・農業の後継者不足に対し真正面から課題解決に取り組んでいる諸団体の皆さんのご苦労を改めて感じています。
活動資金に限りがあるなかで、近年の物価上昇により従来の活動に加え、取り組みの幅を広げていくことはとても難しいのではないでしょうか。本助成制度が少しでもお役に立てることを願い選考をさせていただきました。
ご応募いただいた団体皆さまのご発展とご活躍を祈念いたします。
地域NPO支援組織
今回、山梨地区での応募が例年に比べて多い4件となりました。これは、本助成制度の周知が高まってきた現われであり、関係者の一人として嬉しく思います。
今回の応募事業には、こども家庭庁が推進するこどもまんなかの居場所事業の他、小中学生向けのジェンダー平等プログラムの開発と提供事業、穀物畑をみんなの働く場にするために、雑穀の生産者育成と普及を目指す事業などがあり、「生きるたのしみ、働くよろこび」の創出にチャレンジする取り組みへの計画に大きな魅力を感じ、強い期待を寄せました。
〈中央ろうきん〉山梨県本部
地域・社会におけるさまざまな課題に対して真摯に向き合い、支援・活動している団体が多くあることに驚きを感じつつも、課題解決に向け、熱い思いを持ち活動されていることに感銘を受けました。
今年度は山梨地区としても多くの団体にご応募いただき、どの活動も必要性が高く選考するのは難しかったと感じます。多様性の時代のなかで、潜在ニーズを的確に捉え、活動に「想い」を感じる事業を応援したいと選考しました。
今回ご応募いただいた全ての団体の更なる発展と活動の輪が広がることを祈念いたします。


よく見られているページ